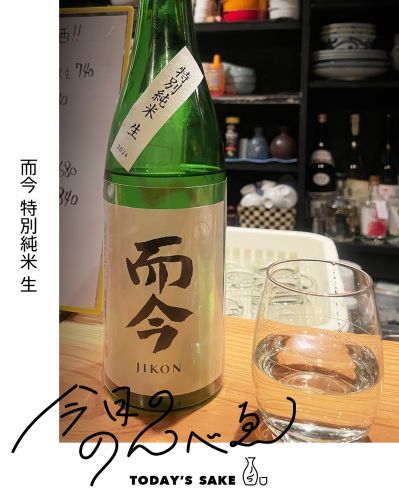ちゃくしょくど
着色度
着色度とは、清酒の色の濃さを測定する指標です。具体的には、430nmの波長の光を酒にあて、その光の吸収の度合いを測定することで得られます。この際、蒸留水を対照として使用し、清酒の厚さが10mmの時の吸光度を基準にします。吸光度の値が大きいほど、酒の色が濃いことを示します。一般的に市販されている清酒の着色度は、0.010から0.035程度とされています。着色度の測定は、品質管理や酒の特性を理解する上で重要な要素の一つです。
清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。
詳細を見る関連用語
-
酵母
酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果た...
-
酒米
「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と...
-
熟成
熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけ...
-
バラ麹
バラ麹とは、粒状でバラバラの形状を持つ米麹の一種です。日本酒の醸造において、麹は糖化を促進する重要な役割を果たします...
-
赤ワイン
赤ワインとは、黒色系または黒紫色系のブドウを原料として作られるワインの一種です。ワイン製造の際には、ブドウの果梗を除...
-
濁り酒
濁り酒とは、発酵過程で生成された酒造りの副産物や雑味成分を完全に取り除かずに、粗い濾過を施した清酒の一種です。一般的...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。