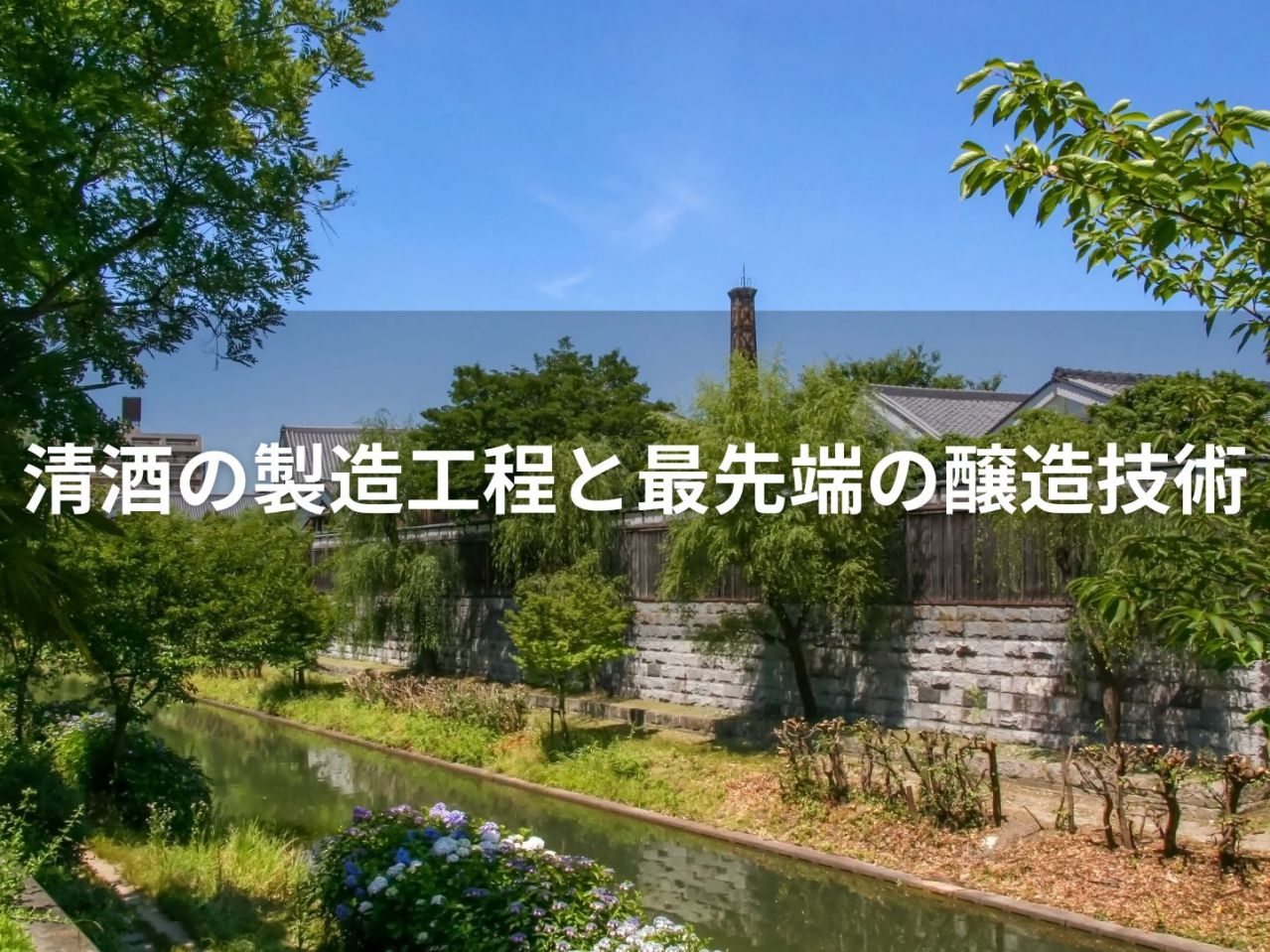
- 日本酒の知識
伝統と革新が交わる瞬間:清酒の製造工程と最先端の醸造技術
日本酒は千年以上の歴史を持つ伝統的な醸造酒であり、その製造工程は今なお進化を続けています。現在、日本酒業界では、最新技術を取り入れながらも伝統の技を守る取り組みが進んでいます。本記事では、清酒の基本的な製造工程を紹介するとともに、近年の技術革新や市場の最新動向についても掘り下げます。
日本酒の基本的な製造工程
日本酒(清酒)の製造は、大きく分けて次の工程で進みます。
(1) 精米 – 米の磨きが品質を決める
清酒は主に「米・水・麹(こうじ)・酵母」から作られます。まず、酒米の外側を削る「精米」が行われます。米の表層にはタンパク質や脂質が多く含まれており、これらが残りすぎると雑味の原因になります。精米歩合(削らずに残す割合)が低いほど、スッキリした味わいの酒に仕上がります。
★ 最新動向 → AIを活用した「精米制御技術」により、従来の技術では難しかった細やかな精米が可能になっています。これにより、より高品質な酒造りが可能に。
(2) 洗米・浸漬・蒸し – 米の準備
精米後の米は水で洗浄し、適度に吸水させた後、蒸します。蒸した米は「麹米」と「掛米」に分けられます。
★ 最新動向 → 温度・湿度を最適に管理するIoT技術が導入され、一年中安定した酒造りが可能に。
(3) 麹造り – 酒の個性を決める
麹は米に「麹菌」を繁殖させたもので、米のでんぷんを糖に分解する役割を持ちます。「一麹、二酛、三造り」と言われるほど、酒の味を決める重要な工程です。
★ 最新動向 → 微生物の動きをデータ化し、最適な環境を維持する「スマート麹室」が登場。従来の杜氏(とうじ)の勘頼みの作業が、データドリブンで管理可能に。
(4) 酒母造り – 酵母を増やす
酒母(しゅぼ)は、発酵をスムーズに進めるためのスターター。ここで酵母が増殖し、アルコール発酵の準備を整えます。代表的な方法には「速醸酛(そくじょうもと)」と「生酛(きもと)」があります。
★ 最新動向 → 特定の風味を引き出す「新規酵母開発」が進み、香りや味わいのバリエーションが広がっています。
(5) もろみ発酵 – アルコールを生み出す
麹米、掛米、水を酒母とともにタンクへ投入し、発酵を進めます。ここで糖化とアルコール発酵が並行して行われる「並行複発酵」が清酒の特徴です。
★ 最新動向 → 温度管理をAIが自動調整する「発酵最適化システム」が開発され、理想的な発酵が安定して行えるようになっています。
(6) 上槽(じょうそう)– 酒と酒粕を分ける
発酵が終わると、「上槽」と呼ばれる工程で、もろみを搾り、酒と酒粕に分けます。伝統的には「槽搾り(ふなしぼり)」や「袋吊り」などの方法があります。
★ 最新動向 → 酒の香味成分を壊さず、効率的に搾れる「遠心分離機」の導入が進んでいます。
(7) 火入れ・貯蔵・瓶詰め – 仕上げの工程
搾った酒は加熱殺菌(火入れ)を行い、風味を安定させます。その後、貯蔵・熟成を経て、瓶詰めされて市場に出ます。
★ 最新動向 → 無加熱でも菌を除去できる「低温除菌技術」が研究され、フレッシュな風味を維持する新技術として注目されています。
近年の酒造技術の革新と市場動向
日本酒業界では、「伝統を守りつつ、技術革新を取り入れる」という流れが加速しています。その背景には、
✅ 海外市場の拡大
→ 清酒の輸出は2023年に400億円超え(国税庁統計)。特にアメリカ、アジア圏での人気が急上昇中。
✅ 多様なスタイルの登場
→ スパークリング日本酒や、低アルコールの日本酒が登場し、若者や海外の消費者にも受け入れられている。
✅ サステナブルな酒造り
→ 酒造りの副産物(酒粕)を再利用した食品開発や、環境負荷の低い醸造プロセスが進んでいる。
✅ テクノロジーの活用
→ AIやIoTの導入で、職人の技を継承しながらも、より安定した高品質な酒造りが可能に。
日本酒造りは、伝統を重んじる一方で、最先端技術を積極的に取り入れています。AI精米、スマート麹室、発酵最適化システムなど、新技術が続々と導入される中で、日本酒はさらなる進化を遂げています。海外市場の拡大やサステナブルな醸造も含め、日本酒の未来はますます明るいものとなるでしょう。
これからの日本酒がどんな進化を遂げるのか、楽しみですね!
関連記事
-

- 日本酒の知識
日本酒は太りやすい?気になる日本酒のカロリーと糖質。他のお酒との比較も!
日本酒は美味しく楽しめる一方で、「糖質やカロリーが高いのでは?」と気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では...
2025/06/06
-

- 日本酒の知識
日本酒の賞味期限はどれくらい?保存場所のポイント
日本酒を買ってみたいけれど、一人で飲み切れるか心配…そんな不安を感じたことはありませんか? 四合瓶や一升瓶といった大き...
2025/05/29
-
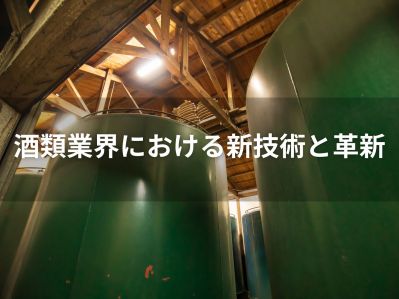
- 日本酒の知識
日本酒の伝統を継承しながら革新へ!AI・IoTが実現する革新的醸造技術とサステナブルな酒造業界の未来展望
日本酒は、長い歴史と伝統の中で育まれてきましたが、昨今は最新技術との融合により、一層の品質向上と効率化、さらには環境...
2025/04/15
-

- 日本酒の知識
酒のしおり | 2024年の日本酒輸出拡大戦略
日本酒の輸出は年々増加しており、特に政府の「2025年までに農林水産物・食品の輸出金額を2兆円、2030年までに5兆円」という...
2025/04/15
-

- 日本酒の知識
酒のしおり | 2024年の日本酒市場動向と課題
日本酒市場は、国内消費の減少と輸出の拡大という二極化した動向を示しています。少子高齢化やライフスタイルの変化による国...
2025/04/15
-

- 日本酒の知識
【日本酒の美味しい飲み方】初心者さんもOK!種類別おすすめ温度&楽しみ方
近年、国内外で人気が高まっている日本酒。 「日本酒に興味はあるけれど、種類が多くてどれを選べば良いか分からない…」 「飲...
2025/04/10
アルコール発酵とは、無酸素の環境下で酵母や細菌が糖類を分解し、エネルギーを生成する過程です。このプロセスでは、ブドウ糖(C6H12O6)が主な基質として利用され、最終的にエチルアルコール(アルコールの主要成分)と炭酸ガスが生成されます。日本酒の製造過程においては、米から得られる糖分が酵母によって発酵され、アルコールと風味豊かな成分が形成されます。このように、アルコール発酵は日本酒の風味や香りを左右する重要なステップです。
詳細を見る並行複発酵(へいこうふくはっこう)とは、日本酒特有の発酵過程を指し、麹菌による澱粉の糖化と酵母によるアルコール発酵が同時に進行する仕組みです。この過程では、糖が生成されると同時にアルコールが生成されるため、糖分が醪(もろみ)に蓄積することがなく、高濃度のアルコールを生み出すことが可能になります。結果として、日本酒の醪が発酵を終えた時点でのアルコール度数は約19度前後に達することが多いです。並行複発酵は、清酒の製造において非常に重要な手法であり、この特性が日本酒の風味や香りに独特の深みを与えてい...
詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...
詳細を見る醸造酒とは、原材料を発酵させることによって作られる酒類の総称です。主に米や麦、ぶどうなどの穀物や果実を使用し、酵母の働きによってアルコールが生成されます。日本酒(清酒)、ビール、ワインなどがこのカテゴリーに含まれます。これらの酒は、発酵による高い香りや味わいを持ち、文化や食事と深く結びついた楽しみ方がされます。醸造酒は、原材料や製造方法によって多様なスタイルが生まれ、各地域の特性を反映したものとなっています。
詳細を見る速醸酛(そくじょうもと)は、現代的な日本酒の醸造方法の一つで、主に淡麗な味わいの日本酒を造る際に用いられます。この手法は、1910年に日本の国立醸造試験所で開発され、現在では約90%の酒母の育成に利用されています。 速醸酛では、醸造用の乳酸を添加することによって、酵母の育成環境を整えます。このため、乳酸菌の自然な活動に依存せず、乳酸菌の副産物による影響を受けることがありません。その結果、速醸酛で造られた日本酒はクリアでさっぱりとした淡麗な酒質に仕上がることが特徴です。この手法により、より安定した品質...
詳細を見る袋吊りは、日本酒の上槽(じょうそう)における伝統的な方法の一つです。この工程では、醪(もろみ)を専用の酒袋に詰め、その袋を吊るして自然に滴り落ちる清酒を集めます。袋吊りでは、圧力をかけることなく、重力を利用してお酒を搾り出すため、非常に繊細な風味を持つ日本酒が得られます。この方法で得られるお酒は、斗瓶囲い(とびんがこい)や雫酒(しずくざけ)とも呼ばれることがあります。袋吊りは、特に高品質な日本酒の生産において重視されており、職人の技術と手間が反映された逸品となることが多いです。
詳細を見る瓶詰めは、日本酒の製造工程の重要なステップであり、清酒を最終的な容器である瓶に詰めることを指します。この工程では、酒が品質を維持したまま消費者に届くように、異物の混入や品質チェックが行われます。また、瓶詰めは通常、清酒の品質を保つために無菌的な環境で行われ、適切な温度管理や衛生状態が重要です。瓶詰め後は、製品としての保管や流通が開始されます。これにより、消費者は新鮮で良質な日本酒を楽しむことができます。
詳細を見る火入れとは、日本酒の製造過程において、上槽(しぼり)後の清酒を60℃から65℃程度に加熱し、殺菌と酵素の働きを停止させる処理です。このプロセスは、日本酒の品質を保つために重要で、貯蔵中の品質劣化を防ぎます。 火入れは、清酒におけるパストゥリゼーションの一環であり、殺菌に加えて香味の調整や酒質の安定化にも寄与します。特に、火入れを行わない日本酒は「生酒」と呼ばれ、火入れされたものと比べて味わいが異なることがあります。このため、火入れは日本酒の保存性と風味を維持するために欠かせない重要な工程です。日本...
詳細を見る麹菌(こうじきん)は、主に日本の伝統的な発酵食品や酒類の製造に使用される糸状菌の一種で、特に麹カビ属に属します。麹菌は、米を蒸して作った蒸米に付着させることで発酵を促進し、米のデンプンを糖化する重要な役割を果たします。このプロセスは、日本酒、味噌、醤油、みりんなどの醸造において不可欠です。 最も一般的に使用される麹菌は「アスペルギルス・オリゼー」で、これは清酒や味噌、しょう油、みりんなどの製造に幅広く利用されます。麹菌が生成する酵素は、米のデンプンをブドウ糖に変化させることで、発酵過程を助け...
詳細を見る麹米(こうじまい)は、酒造りにおいて非常に重要な役割を果たす原料米で、主に麹を作るために使われます。全体の約20%を占め、その品質は日本酒の酒質に大きな影響を与えます。麹米は、一般的に酒造好適米と呼ばれる、品質の高い特別な米が使用されます。これに対して、掛米(かけまい)は主に発酵に使われる米で、通常の米でも使用されることがあります。麹米の重要性は、麹が糖化を助け、アルコール発酵を促進することに起因しており、高品質の麦が求められるため、精米歩合が低いものがよく選ばれます。このように、麹米は日本酒の...
詳細を見る麹室(こうじむろ)とは、麹を製造するための専用の部屋で、特に日本酒の醸造において重要な役割を果たします。この部屋は、麹菌の生育に最適な温度と湿度を維持するために設計されています。一般的に、麹室には主に杉板が使用されており、保温性が高く、結露が起きにくい構造になっています。 麹室には通常、二つの区画(グループ)があり、それぞれ30℃から45℃程度の温度を安定的に保てるように管理されています。また、乾湿度の調整が容易であるため、麹菌の繁殖を促進し、質の高い麹を作る環境が整っています。加えて、室内には温...
詳細を見る雑味とは、日本酒の味わいにおいて不快感を伴う要素を指します。一般的には、味のバランスが崩れた状態において現れるもので、特に苦味や渋みが強く感じられる場合に使われます。これらの雑味は、他の味わいとの調和が取れていない結果として現れるため、清酒の品質や風味の評価において一个重要な指標とされます。清澄な味わいに対して「雑味」は「きたない味」と形容されることもありますが、これは日本酒の本来の旨味や香りが損なわれていることを示唆しています。雑味が多すぎると、日本酒の飲みごたえは損なわれ、満足度は低下す...
詳細を見る酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果たします。日本酒の醸造においては、酵母の種類によって生まれる香りや味わいが大きく変わるため、目的に応じて様々な酵母が使い分けられます。例えば、吟醸酒では芳香成分を多く生成する特性を持つ酵母が使用されることが多いです。このように、酵母は日本酒の風味を左右する重要な要素であり、発酵力が強いことから、醸造やパン製造など多岐にわたって利用されています。酵母の選択が、最終的な製品の品質に大...
詳細を見る酒粕は、日本酒を醸造する際に、醪(もろみ)を圧搾して清酒を取り出した後に残る固形物です。これは、未溶解の米粒や米麹、酵母などが含まれており、栄養価が非常に高い食品です。一般に「清酒粕」または単に「粕」と呼ばれ、さまざまな種類があります。例えば、板状の「板粕」は白くて固形のもので、熟成させた「練り粕」は茶色で柔らかい特徴があります。酒粕は食用として利用されるだけでなく、漬物や菓子、さらには焼酎の原料としても重宝されています。料理に風味や栄養を加える優れた食材です。
詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...
詳細を見る酒母(さかも)は、日本酒を醸造する際に使用される重要な材料で、優れた酵母を大量に培養したものを指します。これは、醪(もろみ)を仕込む前の段階で作られ、醸造の品質や発酵の安定性を確保するために極めて重要です。酒母には、速醸系酒母と生酛系酒母の2種類があります。速醸系酒母は、短期間で酵母を培養できるため、醸造工程が比較的スピーディに進むのが特徴です。一方、生酛系酒母は、自然な酵母の活動を利用して時間をかけて培養され、より複雑で深みのある風味をもたらすことができます。酒母の選び方や培養方法は、最終的...
詳細を見る貯蔵とは、日本酒を火入れした後に一定期間寝かせて香味を熟成させるプロセスを指します。この期間中、日本酒は味や香りがまろやかになり、全体的なバランスが整います。一般的には、タンク内で熟成が行われますが、一部の蔵では瓶詰め後も低温で保管し、瓶貯蔵することがあります。このような貯蔵方法によって、酒質がさらに向上し、独特の風味が増すことが期待されます。
詳細を見る蒸しとは、日本酒の醸造過程において、酒米を加熱処理する工程のことを指します。この工程では、甑(こしき)と呼ばれる蒸し器を使い、米に蒸気を通すことで米を柔らかくしていきます。蒸しによって、米のデンプンが gelatinization(ゼラチン化)し、酵母が糖分を利用しやすくなります。この重要な工程は、酒の風味や香りを形成する基盤となるため、酒造りの中でも欠かせないステップです。
詳細を見る糖化とは、日本酒の製造過程において、米に含まれるでんぷん質を糖に変換する重要なプロセスです。米自体は糖分を含んでいないため、酵母がアルコール発酵を行うためには、まずでんぷんを糖に変える必要があります。この変化は、麹カビが生成する酵素の働きによって実現されます。具体的には、麹の中に含まれるアミラーゼやグルコアミラーゼなどの酵素が、でんぷんをブドウ糖に分解することで、酵母が利用できる形に変えられます。糖化のプロセスは、良質な日本酒を造るために欠かせないステップであり、発酵の効率にも大きな影響を与...
詳細を見る精米とは、玄米の表面を削り、一部の成分を取り除くプロセスを指します。この作業は、日本酒の醸造において非常に重要です。米の表面には、酒に対して悪影響を与える蛋白質や脂質、灰分、さらにはビタミン類などが多く含まれています。これらを取り除くことで、清酒の品質や風味を向上させます。精米は「米をみがく」とも表現され、精米歩合が低くなるほど米が白くキャラクターが際立っていきます。例えば、精米歩合が50%であれば、玄米の50%を削った状態を意味しており、一般的に精米歩合が低いほど高品質な日本酒が醸造されるとされ...
詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。
詳細を見る生酛(きもと)は、日本酒の酒母(もと)を自然の乳酸菌の力を借りて造る伝統的な醸造方法です。この手法は、自然界に存在する乳酸菌を取り入れることで、雑菌の影響を排除し、醗酵に適した環境を整える仕組みとなっています。生酛作りでは、特有の「山卸し」という作業が行われ、これは米をすり潰す工程です。これにより、酵母が活性化しアルコール発酵が促進されます。 この方法は、明治時代以前までは一般的に用いられており、酒造りの重要な工程でしたが、現在ではその伝承が難しくなり、実際に生酛を用いている酒蔵は全体の約1%...
詳細を見る熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけて風味や香りが変化していきます。新酒特有の香りが和らぎ、飲みやすいまろやかな味わいに変わることが特徴です。熟成により、酒の中に含まれる成分が相互に作用し、より深みのあるコクや複雑な旨味を生み出します。熟成は日本酒の魅力を引き出す重要な工程であり、適切な環境下で行われることで、酒質が向上します。
詳細を見る清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。
詳細を見る浸漬とは、日本酒の醸造工程における重要なステップで、洗浄された原料米を蒸す前に仕込み水に浸す作業を指します。このプロセスでは、白米の表面についている糠を水で洗い流し、米が必要とする水分を適切に吸収させます。吸水の時間は、使用する米の品種や年ごとの作柄、米の成分や硬さ、精米の度合いによって変わります。一般的には数分から数時間の間で、米が理想的な水分を含む状態を作り出します。その後、水切りをして次の日の蒸米に備えるのが目的です。浸漬は日本酒の風味や品質に直結するため、非常に重要な作業です。
詳細を見る洗米とは、日本酒の醸造工程において、精米後の原料米を洗浄する作業です。この工程では、白米の表面に付着している糠やその他の不純物を除去することが目的です。この際、洗米に使用する水は、米に水分を浸透させるための給水としても機能します。そのため、洗米の際には給水率を考慮して、浸漬時間を決定する必要があります。 洗米には、洗米機を使用する方法や、水輸送を利用した方法、さらには手作業で行う手洗いの方法があります。洗米によって、米の表面が清潔になるだけでなく、発酵の際に重要な酵素の働きを促進するための準...
詳細を見る杜氏(とうじ)とは、酒蔵において酒造り全般を指揮する最高責任者のことを指します。杜氏は、酒造りを担う職人集団の長であり、酒の品質や製法に大きな影響を与える存在です。地域によって南部杜氏や越後杜氏、丹波杜氏などと呼ばれる杜氏の集団があり、それぞれ異なる伝統や技術を持っています。そのため、杜氏が変わると酒の味やスタイルにも変化が見られることがあります。 近年、杜氏の平均年齢は約65歳に達し、後継者の育成が急務となっています。杜氏は、蔵の運営や醪(もろみ)の仕込み・管理といった重要な業務を行い、日本...
詳細を見る搾りとは、日本酒の製造過程において、醪(もろみ)から清酒を取り出す工程を指します。この過程では、主に「槽による搾り」や「袋吊り」といった方法が用いられます。 「槽による搾り」とは、酒槽と呼ばれる専用の容器に、醪を詰めた酒袋を敷き詰め、その上から圧力をかけて清酒を搾り取る方法です。この手法によって、旨味や香りを豊かに持った清酒が得られます。 もう一つの方法である「袋吊り」は、醪を詰めた袋を吊るし、自然に滴り落ちる清酒を集める方式です。この方法では、重力を利用して清酒がゆっくりと分離され、滑らか...
詳細を見る掛米(かけまい)とは、日本酒の製造において使用される原料米の一つで、全体の約80%を占める重要な要素です。特に酒母やもろみの造りに使用される掛米は、麹米と対になる言葉であり、麹米が全体の約20%を占めるのに対し、掛米は主に発酵過程において酵母が働くための栄養源となります。掛米は通常、蒸きょう後に冷却され、そのまま仕込みに使用されるため、酵母がしっかりと活性化できるように配慮されています。日本酒の味わいや香りの形成において、掛米の種類や品質は非常に重要です。
詳細を見る上槽(じょうそう)は、日本酒の製造過程において完熟した醪(もろみ)を圧搾し、清酒と酒粕に分ける重要な操作を指します。この過程は「搾り(しぼり)」とも呼ばれ、伝統的には酒袋に醪を詰めて槽(ふね)に並べ、重力の力で自然に清酒を抽出する方法が用いられました。 上槽の基本的な流れは次の通りです。まず、醪を約5〜9リットルの酒袋に詰め、槽に並べて積み上げます。この初めに流れ出る濁った清酒を「荒走り(あらばしり)」と呼びます。槽が酒袋でいっぱいになると、上からカサ枠を載せて更に袋を積み重ね、通常約3時間ほど...
詳細を見る麹(こうじ)は、主に米や麦に対して麹菌(こうじきん)を繁殖させたもので、日本酒を始めとする発酵食品の製造に不可欠な役割を果たします。特に日本酒の醸造においては、蒸した米に黄麹菌を育成させた米麹が使用され、この中で生成される酵素が重要です。 麹の成分には、米の中に含まれるデンプンをブドウ糖に変換するためのアミラーゼなどの糖化酵素や、米の蛋白質をアミノ酸に分解するための酵素が含まれています。これにより、米から得られる糖やアミノ酸が酒母やもろみの発酵を助け、日本酒特有の風味や香りを生み出します。 ...
詳細を見る酛(もと)とは、日本酒の造りにおいて非常に重要な要素であり、醪(もろみ)を仕込む前に優れた酵母を大量に培養したものを指します。酛は酒母とも呼ばれ、この工程を酛造りまたは酒母造りといいます。酛の作り方にはさまざまな手法があり、主に速醸酛と生酛に大別されます。 速醸酛は、乳酸を添加することで酵母を育てる手法で、短期間で酒造りを行うことができるため、効率的な醸造が可能です。一方、生酛は、自然に存在する乳酸菌を利用する方法で、伝統的な技術が用いられます。また、山廃酛や菩提酛など、さらに多様な手法もあ...
詳細を見る
