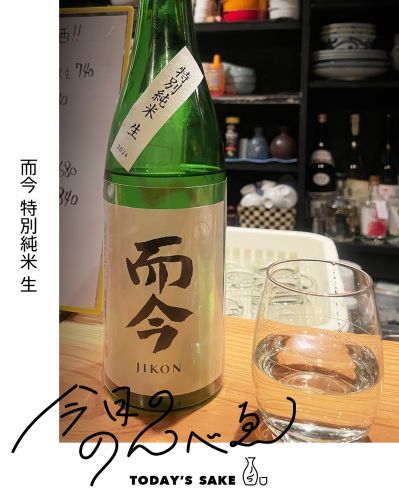外硬内軟
このような蒸米は、高品質な麹(こうじ)を作ったり、もろみを醸造したりするために不可欠な条件とされています。外硬内軟の蒸米は、米が均一に蒸し上げられた結果、この理想的な食感が得られ、酒造りにおいて重要な役割を果たしています。
蒸米とは、麹づくりや酒母、醪(もろみ)造りに用いるために、特別に蒸したお米のことを指します。蒸米は、まず白米を洗浄し、水に浸漬させてから蒸し上げます。このプロセスにより、米は柔らかくなり、酵母や麹菌が働きやすい状態になります。蒸米は、日本酒の醸造において非常に重要な素材であり、酒の風味や香りに大きな影響を与える役割を果たします。
詳細を見る蒸しとは、日本酒の醸造過程において、酒米を加熱処理する工程のことを指します。この工程では、甑(こしき)と呼ばれる蒸し器を使い、米に蒸気を通すことで米を柔らかくしていきます。蒸しによって、米のデンプンが gelatinization(ゼラチン化)し、酵母が糖分を利用しやすくなります。この重要な工程は、酒の風味や香りを形成する基盤となるため、酒造りの中でも欠かせないステップです。
詳細を見る麹(こうじ)は、主に米や麦に対して麹菌(こうじきん)を繁殖させたもので、日本酒を始めとする発酵食品の製造に不可欠な役割を果たします。特に日本酒の醸造においては、蒸した米に黄麹菌を育成させた米麹が使用され、この中で生成される酵素が重要です。 麹の成分には、米の中に含まれるデンプンをブドウ糖に変換するためのアミラーゼなどの糖化酵素や、米の蛋白質をアミノ酸に分解するための酵素が含まれています。これにより、米から得られる糖やアミノ酸が酒母やもろみの発酵を助け、日本酒特有の風味や香りを生み出します。 ...
詳細を見る関連用語
-
酒米
「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と...
-
熟成
熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけ...
-
食中酒
食中酒とは、食事と共に楽しむために選ばれたお酒のことです。料理の味を引き立てたり、香りや風味を相互に補完する役割を果...
-
整粒
整粒(せいりゅう)とは、日本酒の製造過程において、米粒が健全で完全な形状を持つものを指します。この用語は、被害米や死...
-
木香様臭
木香様臭(きこうようしゅう)とは、酒造りの過程において特定の状況で発生する香りの一種です。主に酵母が発酵している際に...
-
特級酒
特級酒とは、かつて日本酒とウイスキーに対して設けられていた税率区分の一つで、清酒の品質を示す指標の一つでした。この制...