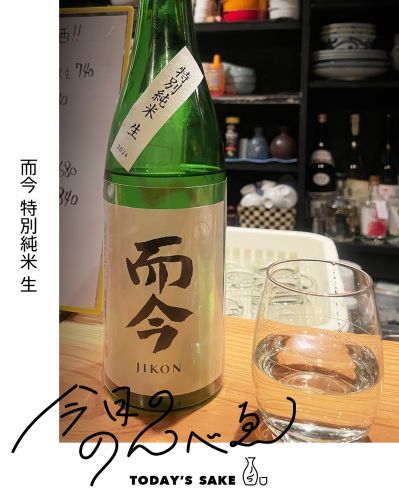短時間浸漬
吟醸酒は、日本酒の特定名称酒の一つであり、原料として精米歩合60%以下の白米、米麹、水、さらに場合によっては醸造アルコールを使用します。吟醸酒は、その製造過程において低温でじっくりと発酵させる「吟醸造り」技法が用いられ、これにより華やかでフルーティーな香りと、すっきりとした淡麗な味わいが特徴となります。 具体的には、精米歩合が60%以下である白米を使用し、香味や色合いが良好な清酒として仕上げられます。醸造アルコールは原料白米の重量の10%を超えない範囲で使用されます。吟醸酒には、純米吟醸酒や大吟醸...
詳細を見る白米とは、玄米から精米され、胚芽や米の表面が削除された米のことを指します。精米の過程で外皮や殻が取り除かれ、主に澱粉部分が残るため、白くて光沢のある状態となります。白米は日本酒の醸造において非常に重要で、精米歩合によって酒の風味や香りに影響を与えるため、特に品質の高い日本酒には厳選された白米が使用されます。一般的には、精米の度合い(粉砕の割合)が低いほど、良質で洗練された酒を生み出す傾向があります。
詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。
詳細を見る浸漬とは、日本酒の醸造工程における重要なステップで、洗浄された原料米を蒸す前に仕込み水に浸す作業を指します。このプロセスでは、白米の表面についている糠を水で洗い流し、米が必要とする水分を適切に吸収させます。吸水の時間は、使用する米の品種や年ごとの作柄、米の成分や硬さ、精米の度合いによって変わります。一般的には数分から数時間の間で、米が理想的な水分を含む状態を作り出します。その後、水切りをして次の日の蒸米に備えるのが目的です。浸漬は日本酒の風味や品質に直結するため、非常に重要な作業です。
詳細を見る関連用語
-
麹
麹(こうじ)は、主に米や麦に対して麹菌(こうじきん)を繁殖させたもので、日本酒を始めとする発酵食品の製造に不可欠な役...
-
精米
精米とは、玄米の表面を削り、一部の成分を取り除くプロセスを指します。この作業は、日本酒の醸造において非常に重要です。...
-
発酵
発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...
-
醪
醪(もろみ)とは、日本酒の醸造過程における主発酵の状態を指す用語です。酒母(しゅぼ)、麹(こうじ)、蒸米(むしまい)...
-
異臭
異臭とは、日本酒において通常の香りとは異なる、嫌な臭いのことを指します。正常な清酒には存在しない、発酵過程や保存状態...
-
マリアージュ
マリアージュとは、特定の飲食物同士が互いに引き立て合い、新たな風味や体験を生み出す組み合わせのことを指します。日本酒...