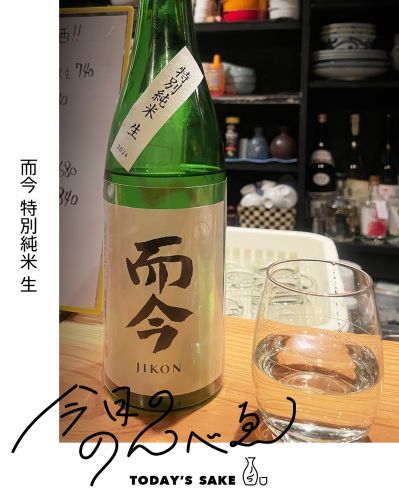アルコール使用限度数量
原料用アルコールとは、日本の酒税法により規定された、酒類製造のための原材料として使用されるアルコールのことを指します。特に清酒の製造に関しては、原料用アルコールには連続蒸留機で製造されたアルコールが含まれます。また、昭和62酒造年度以降の改正により、米、米麹、清酒、または清酒粕を原材料とした焼酎乙類(自製酒や委託製造、共同製造が条件)も原料用アルコールとして認められています。このように原料用アルコールは、清酒の製造において重要な役割を果たしており、酒類の品質や風味に影響を与える要素となっています。
詳細を見る酒造年度(さかぞうねんど)とは、日本の日本酒における醸造期間を指し、毎年7月1日から翌年の6月30日までの1年間を1酒造年度と定めています。この期間は新酒製造の開始日からの区切りであり、業界内では「BY」(Brewery Year)と略されることが一般的です。例えば、平成29年の7月1日から翌年の6月30日までに醸造された日本酒は「29BY」と表記されます。このように、酒造年度は日本酒の製造や流通における重要な指標の一つとなっています。なお、使用される年の表記は元号で、国や文化により異なるため、国外ではこのアプローチが理解...
詳細を見る白米とは、玄米から精米され、胚芽や米の表面が削除された米のことを指します。精米の過程で外皮や殻が取り除かれ、主に澱粉部分が残るため、白くて光沢のある状態となります。白米は日本酒の醸造において非常に重要で、精米歩合によって酒の風味や香りに影響を与えるため、特に品質の高い日本酒には厳選された白米が使用されます。一般的には、精米の度合い(粉砕の割合)が低いほど、良質で洗練された酒を生み出す傾向があります。
詳細を見る清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。
詳細を見る関連用語
-
アルコール度数
アルコール度数とは、酒類に含まれるエチルアルコールの容量割合を指します。これは一般的に、酒の持つアルコールの濃度を示...
-
酒類
酒類とは、アルコールを含む飲料の総称であり、一般的には酒税法に基づいて定義されています。具体的には、アルコール分が1度...
-
精白
精白とは、玄米の表層部分にあるぬかや皮を取り除き、白い米にする工程を指します。このプロセスは日本酒の製造において非常...
-
下面酵母
下面酵母(しためこうぼ)は、発酵プロセスの後半において、重力によって下に沈殿する特性を持つ酵母の一種です。通常、ビー...
-
過酸化水素水
過酸化水素水は、主に消毒や殺菌に用いられる化学物質です。一般的には30~35%の濃度で販売されており、この濃度の過酸化水...
-
割水
割水とは、日本酒の製造過程において、熟成された原酒に水を加える作業を指します。この作業は、主にアルコール度数や香味の...