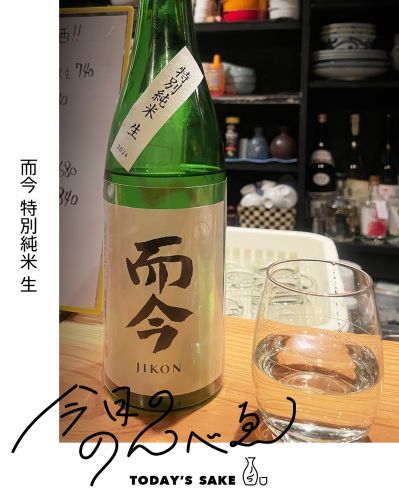べくはい
可杯
可杯(かはい)は、形状が特徴的な酒器で、通常は円形の底がなく、持ち上げて飲む際に酒が溢れないように設計されています。この器は、指で押さえたり、手のひらで支えたりしない限り、酒が漏れてしまうため、飲む際には一気に飲み切ることが求められます。こうした特性から、可杯は楽しい飲み会や特別な場での日本酒を楽しむためのアイテムとして使われることが多いです。また、可杯を使用することで、飲むときの緊張感や楽しみが増すことが魅力の一つです。
酒器とは、日本酒を運んだり飲むために使用する器や容器のことで、さまざまな形状や材質があります。代表的な酒器には、猪口(ちょこ)やぐい呑(ぐいのみ)、盃(さかずき)、グラスがあり、これらは主に日本酒を飲むために用いられます。また、徳利(とっくり)や銚子(ちょうし)、片口(かたくち)などは日本酒を注ぐための容器です。酒器の選び方や使い方には、酒の種類や飲むシーンによって工夫がされることも多く、その個性や美しさが日本酒の楽しみをさらに深めます。
詳細を見る関連用語
-
酒器
酒器とは、日本酒を運んだり飲むために使用する器や容器のことで、さまざまな形状や材質があります。代表的な酒器には、猪口...
-
坊主
「坊主(ぼうず)」とは、日本酒の醪(もろみ)において発酵が進んだ際の泡の状態の一つで、醪の表面に何も浮かんでいない状...
-
浮遊物質量
浮遊物質量とは、水中に浮いている固形物の量を指し、主に水の清浄度や汚染度を示す指標の一つです。この指標は、BOD(生物化...
-
槽
槽(ふね)とは、日本酒の製造過程において、醪(もろみ)を圧搾して清酒と酒粕に分離するために使用される設備を指します。...
-
きれい
「きれい」とは、日本酒の味わいや香りがすっきりとしていて、飲みやすいことを指し、しばしば「淡麗」とも表現されます。雑...
-
規定濃度
単語:規定濃度 規定濃度とは、特定の化学物質の濃度を示す基準の一つで、通常は1リットルの溶液中に含まれる溶質の量を示し...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。