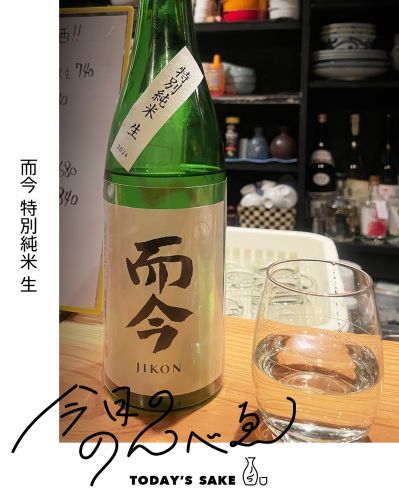貯蔵年数
製法品質表示基準とは、日本酒(清酒)の製造方法や品質に関する情報を消費者に正確に伝えるための基準を指します。この基準に従って、各銘柄は酒の原料や製造過程、特性などを表示しなければなりません。具体的には、使用される米の種類、精米歩合、水の源、製造方法(例:普通酒、純米酒、吟醸酒など)、アルコール度数などが含まれます。これにより消費者は自分の好みに合った日本酒を選ぶことができ、また透明性のある市場を促進することが目的とされています。製法品質表示基準は、日本酒の品質を鑑みる重要な要素であり、信頼性...
詳細を見る貯蔵とは、日本酒を火入れした後に一定期間寝かせて香味を熟成させるプロセスを指します。この期間中、日本酒は味や香りがまろやかになり、全体的なバランスが整います。一般的には、タンク内で熟成が行われますが、一部の蔵では瓶詰め後も低温で保管し、瓶貯蔵することがあります。このような貯蔵方法によって、酒質がさらに向上し、独特の風味が増すことが期待されます。
詳細を見る関連用語
-
酸度
酸度は、日本酒に含まれる酸の量を示す指標であり、通常は1.0〜2.0の範囲で表されます。この数字が大きいほど、日本酒におけ...
-
熟成
熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけ...
-
混合指示薬
混合指示薬とは、特定のpH範囲に応じて色が変わる物質を混合したものです。日本酒の酸度を測定する際には、ブロムチモール・...
-
ホルマリン
ホルマリンとは、主にホルムアルデヒドを約40%含む無色の液体で、特有の刺激臭があります。日本酒の製造過程では、麹室にお...
-
添桶
添桶(そえおけ)は、日本酒の製造過程において添仕込みに使用される専用の容器です。添仕込みとは、発酵中のもろみ(発酵中...
-
米置き
米置きとは、蒸米を作る過程において、浸漬した白米を甑(こしき)の中に入れる作業を指します。この工程では、まず白米を水...