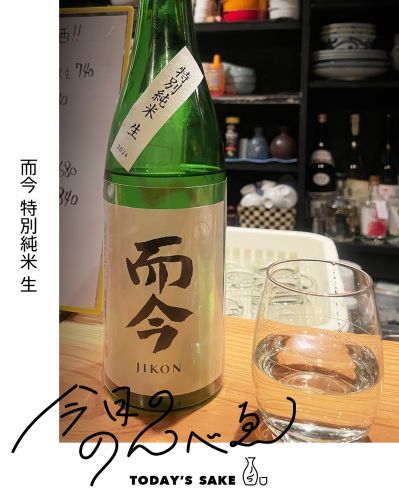ドメーヌ
仕込み水とは、日本酒を醸造する際に、特に仕込み工程で使用される水のことを指します。この水は、酒質に大きな影響を及ぼすため、選ばれる際にはさまざまな条件が考慮されます。具体的には、酵母の成長に必要なミネラル成分—カリウムやマグネシウムなど—を適度に含んでいることが重要です。また、酒の色合いや風味に影響を与える鉄分やマンガンなどは、できるだけ含まれないことが望まれます。仕込み水は蒸米や麹と共に仕込みに使われ、酒母タンクや醪(もろみ)タンクに注がれるため、日本酒造りにおいて全体の味わいや香りを決定づ...
詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...
詳細を見る関連用語
-
責め
「責め」とは、日本酒の上槽工程における重要な作業の一つです。具体的には、醪(もろみ)を詰めた酒袋を酒槽に敷き詰めた後...
-
食品衛生法
食品衛生法は、日本における食品の安全性を確保するための法律です。この法律は、食品が原因となる衛生上の危害を防ぎ、公衆...
-
糖化
糖化とは、日本酒の製造過程において、米に含まれるでんぷん質を糖に変換する重要なプロセスです。米自体は糖分を含んでいな...
-
ヤブタ
ヤブタとは、日本酒の製造過程において用いられる「ヤブタ式自動圧搾機」を指します。この機械は、上槽(じょうそう)と呼ば...
-
特定低品位米
特定低品位米とは、特に品質基準を満たさないとされる米のことを指します。この米は、一般的に食品としての利用が制限され、...
-
βー澱粉
βー澱粉とは、澱粉の一種で、特に水分を含んだ状態のことを指します。澱粉は、主に植物に存在する多糖類で、主にエネルギー源...