
- ニュース・トピック
ユネスコが認めた日本の酒文化!「伝統的酒造り」登録の意義と未来
2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。日本酒、焼酎、泡盛の製造技術を含むこの伝統文化は、地域性と歴史が息づく重要な遺産です。この登録は、国際的な認知を得ると同時に、文化の継承と発展を促す契機となるでしょう。
2024年12月5日、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に正式登録されました。この決定は、パラグアイのルケで開催された第19回政府間委員会において、全会一致で承認されたものです。
「伝統的酒造り」は、日本酒、焼酎、泡盛などの製造技術を指し、500年以上前にその原型が確立されました。これらの技術は、米や麦などの穀物を原料とし、伝統的なこうじ菌を使用することが特徴です。各地域の気候風土に応じて発展し、杜氏や蔵人たちが五感を駆使して手作業で製造しています。
ユネスコの無形文化遺産への登録は、これらの伝統的技術が日本の文化や社会において重要な役割を果たしていることを国際的に認められたことを意味します。特に、日本酒は結婚式や祭りなどの儀式で欠かせない存在であり、焼酎や泡盛も地域の文化や生活に深く根付いています。
この登録により、国内外での日本酒や焼酎、泡盛への関心が高まることが期待されています。特に、若い世代や海外市場での需要拡大が見込まれ、伝統的な酒造りの技術と文化の継承・発展に寄与するでしょう。
日本酒造組合中央会などの業界団体は、今回の登録を契機に、伝統的酒造りの魅力を国内外に発信し、さらなる普及と発展を目指しています。また、政府も輸出促進や観光資源としての活用を進める方針です。
「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録は、日本の酒文化の価値を再認識し、未来へとつなげる大きな一歩となりました。これを機に、日本酒や焼酎、泡盛の魅力を再発見し、その深い味わいと歴史に触れてみてはいかがでしょうか。
関連記事
-

- ニュース・トピック
フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―
2025/07/10
-

- ニュース・トピック
赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~
2025/07/08
-
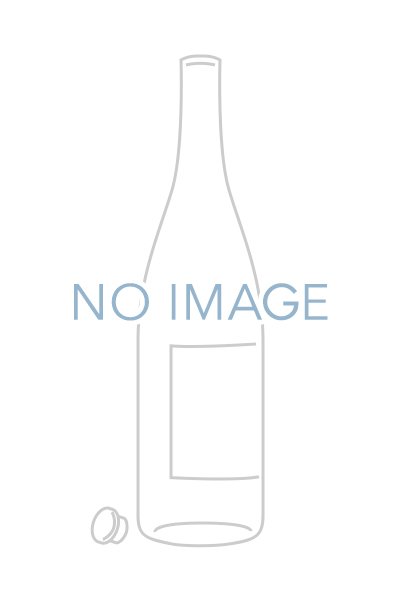
- ニュース・トピック
【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始
2025/07/08
日本酒造組合中央会は、清酒製造業者によって組織された全国的な団体で、酒類業組合法に基づいて設立されました。この会の主な目的は、酒税の保全と酒類業界の取引の安定を図ることです。特に、会員同士の緊密な連絡と相互協力を重視し、円滑な納税を促進することにより、業界全体の安定性と健全な発展を目指しています。 日本酒造組合中央会は、清酒製造業者に対して自主的かつ公正な事業活動の振興を支援し、共同の利益を増進するための様々な事業を行っています。さらに、この組織は毎年10月1日を「日本酒の日」と定めており、日本...
詳細を見る蔵人(くらびと)とは、日本酒を製造する酒蔵で、実際に醪(もろみ)づくりに従事する職人のことを指します。彼らは、杜氏(とうじ)と呼ばれる技術責任者の指導のもと、酒の仕込みや発酵管理などを行い、高品質の清酒を生み出す重要な役割を担っています。蔵人は伝統的な技術や知識を継承し、時には新しい製法を取り入れながら、米、水、酵母という基本的な原料から日本酒を造る熟練の技術者です。日本酒の風味や品質は、蔵人の技術と情熱によって大きく左右されます。
詳細を見る焼酎とは、日本の伝統的な蒸留酒であり、主に二つのカテゴリーに分類されます。甲類焼酎は連続式蒸留機を使用し、アルコール分は36度未満で、一般的にホワイトリカーと呼ばれています。乙類焼酎は単式蒸留機を使用し、アルコール分は45度以下で、本格焼酎とされます。焼酎はウイスキーやブランデーなどの蒸留酒とは異なるため、法律上別のカテゴリに分類されています。 また、焼酎にはさまざまな種類があり、乙類焼酎の場合、主原料によって多様な製品が存在します。例えば、米を主原料とする米焼酎、さつまいもを使ったいも焼酎、麦...
詳細を見る泡盛は、沖縄県を中心とする琉球諸島特産の伝統的な蒸留酒です。主にタイから輸入された砕米を原料にし、アワモリ麹菌(アスペルギルス・オリゼーの一種)を使用して作られる麦麹を利用します。泡盛の製造過程では、掛米を使わず、麹のみで糖化を行い、その後に発酵させます。発酵したものは、単式蒸留機を用いて蒸留されるため、非常に濃厚で独特の風味を持ちます。泡盛は、その特異な製法と風味から、飲み方や料理との相性も多様で、沖縄の文化に深く根付いています。アルコール度数は一般的に高く、香りや味わいのバリエーションが...
詳細を見る杜氏(とうじ)とは、酒蔵において酒造り全般を指揮する最高責任者のことを指します。杜氏は、酒造りを担う職人集団の長であり、酒の品質や製法に大きな影響を与える存在です。地域によって南部杜氏や越後杜氏、丹波杜氏などと呼ばれる杜氏の集団があり、それぞれ異なる伝統や技術を持っています。そのため、杜氏が変わると酒の味やスタイルにも変化が見られることがあります。 近年、杜氏の平均年齢は約65歳に達し、後継者の育成が急務となっています。杜氏は、蔵の運営や醪(もろみ)の仕込み・管理といった重要な業務を行い、日本...
詳細を見る
