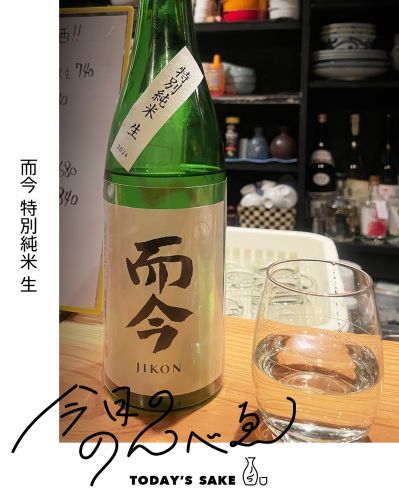いちこく
一石
一石(いっせき)とは、日本酒の計量単位の一つで、約180リットルに相当します。この単位は、昔から日本の伝統的な米や酒の量を測るために使われてきました。一石は、十斗(じゅっと)とも等しい関係にあります。日本酒の醸造や流通においては、一石の単位が使用されることが多く、酒造業界では重要な指標となっています。
関連用語
-
アルコール
アルコールは、有機化合物の一種で、分子中に水酸基(-OH)を含むことが特徴です。一般的に、1つの水酸基を持つものを「1価ア...
-
一合
一合(いちごう)とは、日本酒を計量するための単位の一つで、180ミリリットル(ml)に相当します。また、一合は十勺(しゃく...
-
一升
一升(いっしょう)は、日本の伝統的な容量の単位で、主に日本酒の測定に使用されます。一升は約1.8039リットルに相当し、こ...
-
酵母
酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果た...
-
仕込み
仕込みとは、日本酒の醸造過程における重要な工程で、原材料である麹、蒸米、水を混ぜ合わせて、酛(酒母)や醪(もろみ)を...
-
酒米
「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。