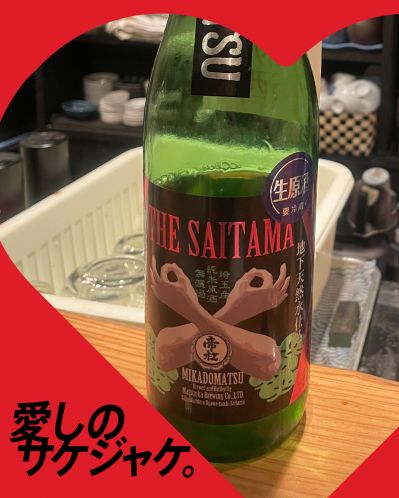たるざけ
たる酒
たる酒とは、主に杉樽で貯蔵された日本酒の一種で、その特徴として清涼な香りが挙げられます。特に奈良県の吉野杉で貯蔵されたものは高い評価を受けており、杉の香りが酒に移ることで独特の風味を持つようになります。かつては日本酒の貯蔵には杉の樽が一般的に使用されており、昭和初期まではほとんどの日本酒がこの方法で製造されていました。しかし、現在ではホーロータンクのような、酒に影響を与えない貯蔵方法が普及してきています。これにより、たる酒特有の風味も変化しており、さまざまなスタイルの日本酒が楽しめるようになっています。
貯蔵とは、日本酒を火入れした後に一定期間寝かせて香味を熟成させるプロセスを指します。この期間中、日本酒は味や香りがまろやかになり、全体的なバランスが整います。一般的には、タンク内で熟成が行われますが、一部の蔵では瓶詰め後も低温で保管し、瓶貯蔵することがあります。このような貯蔵方法によって、酒質がさらに向上し、独特の風味が増すことが期待されます。
詳細を見る関連用語
-
熟成
熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけ...
-
発酵
発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...
-
下灘目郷
下灘目郷(しもなだめごう)は、かつて存在した日本酒の産地であり、特に明和年間(1764年〜1772年)に「灘目三郷」として知...
-
出麹歩合
出麹歩合とは、出麹の吸水率を示す指標であり、出麹に使用された米の量とそれに対する白米の量の割合を表します。出麹歩合は...
-
粒状炭
粒状炭は、日本酒の製造過程において重要な役割を果たす炭素素材です。主に仕込用水や割水用水の精製、清酒の脱色、香味の調...
-
仕込配合
仕込配合とは、日本酒を造る際に必要な原料の比率や量を示すものです。この配合には、使用する白米、水、アルコールの量が含...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。