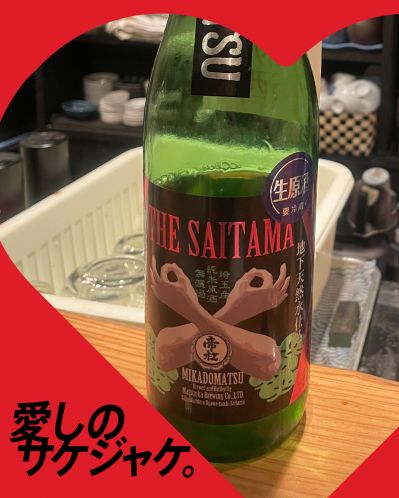はな
ハナ
ハナとは、日本酒をきき酒する際に、鼻孔を通じて感じる香りのことを指します。日本酒の香りにはさまざまな種類があり、フルーティーさや floral(花のような)香、穀物のような香りなどがあります。ハナは日本酒のクオリティや個性を理解する上で非常に重要な要素とされており、酒を味わう際にはまずこの香りを楽しむことが推奨されます。日本酒の香りを正しく感じ取ることで、その酒の特徴や製造過程に対する理解を深めることができます。
きき酒(ききざけまたはききしゅ)は、日本酒の官能検査の一環として行われる評価手法のことを指します。このプロセスでは、まず日本酒の色や透明度を観察し、外観の良否を判断します。次に、酒の香りを嗅ぎ、そこから複雑な香りの要素を識別します。そして、最後に口に含んで味を確認し、甘味、酸味、苦味、旨味などのバランスを評価します。このように、色、香り、味の三つの要素を総合的に評価することで、日本酒の品質や特徴を明らかにし、格付けや数量化を行うことができます。きき酒は、より深く日本酒を理解するための重要な技...
詳細を見る関連用語
-
酵母
酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果た...
-
発酵
発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...
-
木香
木香(きこう)とは、日本酒の製造や貯蔵過程において、木製の容器、特に杉の木桶を使用することによって日本酒に移ってくる...
-
米糠
米糠(こめぬか)は、玄米を精米する過程で取り除かれる外皮や胚芽部分からなる副産物です。精米歩合に応じて、赤糠(あかぬ...
-
醸造用水
醸造用水とは、日本酒の製造過程において使用される水のことです。具体的には、洗米・浸漬用水、仕込用水、及び雑用用水の3...
-
地酒
地酒(じざけ)とは、特定の地域で生産された日本酒を指します。通常、その地域の気候や水質、地元の米を使用して醸造される...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。