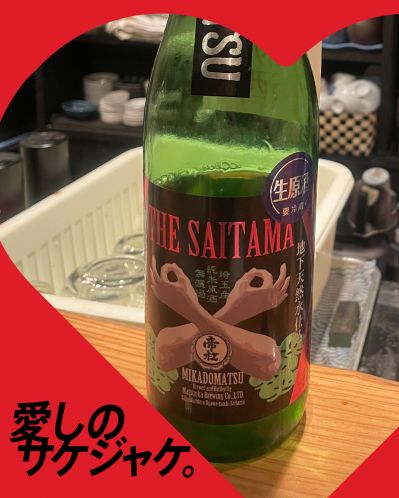実米
精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...
詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...
詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。
詳細を見る掛米(かけまい)とは、日本酒の製造において使用される原料米の一つで、全体の約80%を占める重要な要素です。特に酒母やもろみの造りに使用される掛米は、麹米と対になる言葉であり、麹米が全体の約20%を占めるのに対し、掛米は主に発酵過程において酵母が働くための栄養源となります。掛米は通常、蒸きょう後に冷却され、そのまま仕込みに使用されるため、酵母がしっかりと活性化できるように配慮されています。日本酒の味わいや香りの形成において、掛米の種類や品質は非常に重要です。
詳細を見る関連用語
-
規定濃度
単語:規定濃度 規定濃度とは、特定の化学物質の濃度を示す基準の一つで、通常は1リットルの溶液中に含まれる溶質の量を示し...
-
どぶろく
どぶろくは、濁酒とも呼ばれ、米を発酵させて造られる日本酒の一種です。この酒は、醪(もろみ)を濾さずにそのまま瓶詰めさ...
-
アルコール
アルコールは、有機化合物の一種で、分子中に水酸基(-OH)を含むことが特徴です。一般的に、1つの水酸基を持つものを「1価ア...
-
槽
槽(ふね)とは、日本酒の製造過程において、醪(もろみ)を圧搾して清酒と酒粕に分離するために使用される設備を指します。...
-
瓶内二次発酵方式
瓶内二次発酵方式とは、発泡清酒を製造する際の手法の一つです。この製法では、アルコール発酵が終わっていない状態の醪(も...
-
もと
「もと」とは、日本酒の製造過程において重要な役割を果たす「酒母」(しゅぼ)を指します。酒母は、醸造の初期段階で作られ...