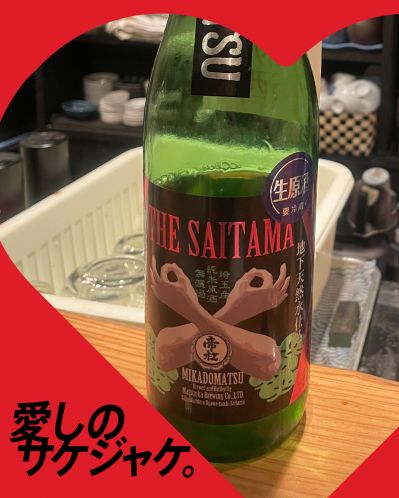飛沫同伴
仕込みとは、日本酒の醸造過程における重要な工程で、原材料である麹、蒸米、水を混ぜ合わせて、酛(酒母)や醪(もろみ)を作ることを指します。この過程では、まず水と麹を混ぜた「水麹」に蒸米を加え、混ぜ合わせて一定の温度に保ちます。この温度管理が、発酵の進行に大きな影響を与え、酒の風味や香りを決定づけるため非常に重要です。仕込みは通常、数回に分けて行われ、最終的に醪が形成され、アルコール発酵が進行します。
詳細を見る蒸しとは、日本酒の醸造過程において、酒米を加熱処理する工程のことを指します。この工程では、甑(こしき)と呼ばれる蒸し器を使い、米に蒸気を通すことで米を柔らかくしていきます。蒸しによって、米のデンプンが gelatinization(ゼラチン化)し、酵母が糖分を利用しやすくなります。この重要な工程は、酒の風味や香りを形成する基盤となるため、酒造りの中でも欠かせないステップです。
詳細を見る和釜(わがま)は、主に日本酒の製造過程で用いられる伝統的な蒸し器の一種です。特に三州釜として知られるこの器具は、米を蒸すために使用され、清酒の醸造において重要な役割を果たします。和釜は通常、鉄製、アルミニウム製、またはステンレス製の素材で作られており、それぞれに特有の特性があります。例えば、鉄製の和釜は熱伝導が良く、安定した温度管理が可能なため、米を均一に蒸すことができます。和釜を使用することで、米の淹れ方や香りが向上し、日本酒の品質向上に寄与しています。
詳細を見る甑(こしき)とは、日本酒の製造過程において、原料米を蒸すために使用される道具です。一般に桶状の形をしていますが、底に「甑穴」と呼ばれる穴が開いており、ここから蒸気が上昇して米を均等に蒸し上げる仕組みになっています。伝統的には杉材で作られていましたが、最近では軽量で耐久性のあるアルミニウムやステンレス製の甑が主流になっています。また、現代ではコンベア式の連続蒸米機も多く採用されており、効率的な蒸し工程が実現されています。甑を用いた蒸し工程は、米の澱粉を gelatinize(ゼラチン化)し、日本酒の醸造に...
詳細を見る関連用語
-
雑味
雑味とは、日本酒の味わいにおいて不快感を伴う要素を指します。一般的には、味のバランスが崩れた状態において現れるもので...
-
発酵
発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコー...
-
仲(仲添)
「仲(仲添)」とは、日本酒の醸造プロセスにおいて、仲仕込み(なかじこみ)と呼ばれる段階を指します。仲仕込みは、最初の...
-
黄麹
黄麹(おうこうじ)とは、日本酒の醸造に使用される麹菌の一種であり、その胞子が黄色または黄緑色を呈します。黄麹は、主に...
-
袋吊り
袋吊りは、日本酒の上槽(じょうそう)における伝統的な方法の一つです。この工程では、醪(もろみ)を専用の酒袋に詰め、そ...
-
多糖類
多糖類とは、数十から数千の単糖類が結合してできた高分子化合物のことです。日本酒の製造過程では、米や米麹のデンプンが酵...