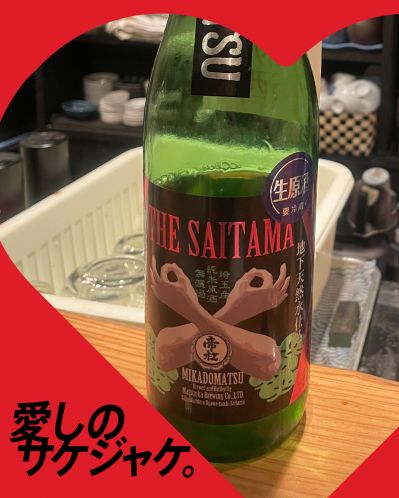農産物検査法
醸造用玄米とは、日本酒の製造に特化したお米のことを指します。これは農産物検査法に基づき、清酒の製造に適した特別な規格が設けられており、通常の水稲うるち米とは異なります。醸造用玄米は、特上から3等までおよび等外の合計6段階に等級が分けられ、品質や用途に応じた評価がなされます。代表的な品種には、酒造りにおいて特に人気のある山田錦、五百万石、美山錦、そして八反錦1号などがあり、これらは酒質に大きく影響を与えるため、選ばれる理由となっています。日本酒の特性や風味を決定づける重要な要素となる醸造用玄米は、...
詳細を見る玄米とは、稲の籾から脱穀され、籾殻が取り除かれた状態の米のことを指します。玄米は、白米と異なり、外皮や胚芽が残っているため、栄養価が高く、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。このため、健康志向の高まりを受けて、玄米を使った日本酒も増えてきています。日本酒の製造においては、玄米を使用した場合、白米よりも香りや味わいに独自の特性が出ることが多く、個性的な日本酒を楽しむことができます。
詳細を見る関連用語
-
利猪口
利猪口(りちょく)は、清酒の試飲(きき酒)に使用される特別な容器です。一般的には、白磁製で底に藍色の蛇の目模様が施さ...
-
酛立て
酛立てとは、日本酒の酒母(しゅぼ)造りにおける重要な工程の一つで、最初に麹(こうじ)、蒸米(むしごめ)、仕込み水を混...
-
釜屋
釜屋(かまや)とは、日本酒の製造過程において重要な役割を担う蔵人の一つです。釜屋は主に蒸米作業を担当し、米を蒸すプロ...
-
赤色酵母
赤色酵母は、人工的に突然変異を引き起こして得られた酵母で、特徴的な赤色の色素を菌体内に蓄積します。この酵母は特に桃色...
-
散布図
散布図とは、2つの異なる測定値を持つ多数の試料を視覚的に表現するための図です。横軸に1つの測定値(x)、縦軸に別の測定値...
-
愛山
愛山(あいやま)は、日本酒の酒造好適米の一つで、主に兵庫県で栽培されています。この米は、晩生品種であり、成熟に時間が...