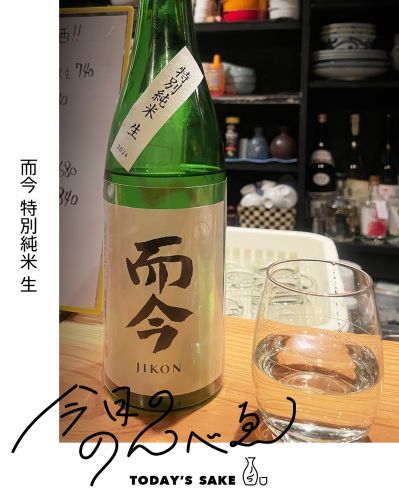さんてんほう
3点法
3点法とは、異なる2種類の日本酒の違いを確かめるためのテイスティング手法です。この方法では、テイスターに3つの酒を提示します。具体的には、酒Aを2つ、酒Bを1つ用意し、テイスターに「異なる酒はどれか」を指摘させます。この方式が使われる理由は、感覚のバイアスを減らし、より客観的に味や香りの違いを評価できるからです。3点法は、特に酒の評価を行う際に有用で、消費者の嗜好やプロフェッショナルの評価を得るために広く利用されています。
関連用語
-
アルコール度数
アルコール度数とは、酒類に含まれるエチルアルコールの容量割合を指します。これは一般的に、酒の持つアルコールの濃度を示...
-
酸度
酸度は、日本酒に含まれる酸の量を示す指標であり、通常は1.0〜2.0の範囲で表されます。この数字が大きいほど、日本酒におけ...
-
酒米
「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と...
-
清酒
清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄...
-
半仕舞
半仕舞(はんじまい)とは、日本酒の仕込みにおいて、1日おきに醪(もろみ)を1本ずつ仕込む作業のことを指します。この方法...
-
どぶろく
どぶろくは、濁酒とも呼ばれ、米を発酵させて造られる日本酒の一種です。この酒は、醪(もろみ)を濾さずにそのまま瓶詰めさ...
※ 本ページは一般的な用語解説です。実際の表示や基準は商品・酒蔵により異なる場合があります。