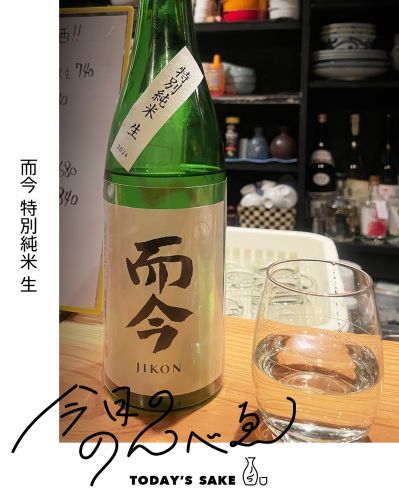汲出し四段
四段仕込みとは、日本酒を醸造する際の特別な仕込方法の一つです。この手法は、主に甘口の日本酒を造るために用いられます。基本的には、三段仕込みで作った醪(もろみ)が完成に近づいた段階で、最後の四段目として蒸米を新たに加えることから名付けられています。 四段仕込みにはさまざまなバリエーションがあり、例えば「酵素四段」や「うるち米四段」、「もち米四段」などがあります。それぞれの手法によって、最終的な味わいや風味が異なるため、酒造りには多様な技術と工夫が求められます。このように、四段仕込みは多様な可能...
詳細を見る親桶(おやおけ)とは、日本酒の製造過程において使用される大きな容器のことを指します。醪(もろみ)の温度管理を容易にするため、醪を1本の大容器に仕込むのではなく、複数の小容器に分けて仕込むことが一般的です。このとき、大容器が親桶と呼ばれ、その付属にあたる小さな容器は枝桶(えだおけ)と呼ばれます。親桶は、主に発酵過程での温度調整や管理がしやすくするために利用され、質の高い日本酒を生産するための重要な役割を果たしています。
詳細を見る蒸米とは、麹づくりや酒母、醪(もろみ)造りに用いるために、特別に蒸したお米のことを指します。蒸米は、まず白米を洗浄し、水に浸漬させてから蒸し上げます。このプロセスにより、米は柔らかくなり、酵母や麹菌が働きやすい状態になります。蒸米は、日本酒の醸造において非常に重要な素材であり、酒の風味や香りに大きな影響を与える役割を果たします。
詳細を見る糖化とは、日本酒の製造過程において、米に含まれるでんぷん質を糖に変換する重要なプロセスです。米自体は糖分を含んでいないため、酵母がアルコール発酵を行うためには、まずでんぷんを糖に変える必要があります。この変化は、麹カビが生成する酵素の働きによって実現されます。具体的には、麹の中に含まれるアミラーゼやグルコアミラーゼなどの酵素が、でんぷんをブドウ糖に分解することで、酵母が利用できる形に変えられます。糖化のプロセスは、良質な日本酒を造るために欠かせないステップであり、発酵の効率にも大きな影響を与...
詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。
詳細を見る枝桶(えだおけ)とは、日本酒の醸造過程において使用される小型の容器のことです。この用語は、主に大きな容器である親桶(おやおけ)から派生しており、醪(もろみ)の温度管理を容易にするために、1本の大きな容器ではなく、複数の小さな容器に分けて酒を仕込む際に用いられます。枝桶を使用することで、温度の均一化や発酵の進行状況をより細かく調整することができ、品質の向上につながります。このように、枝桶は日本酒の製造において重要な役割を果たしています。
詳細を見る搾りとは、日本酒の製造過程において、醪(もろみ)から清酒を取り出す工程を指します。この過程では、主に「槽による搾り」や「袋吊り」といった方法が用いられます。 「槽による搾り」とは、酒槽と呼ばれる専用の容器に、醪を詰めた酒袋を敷き詰め、その上から圧力をかけて清酒を搾り取る方法です。この手法によって、旨味や香りを豊かに持った清酒が得られます。 もう一つの方法である「袋吊り」は、醪を詰めた袋を吊るし、自然に滴り落ちる清酒を集める方式です。この方法では、重力を利用して清酒がゆっくりと分離され、滑らか...
詳細を見る醪(もろみ)とは、日本酒の醸造過程における主発酵の状態を指す用語です。酒母(しゅぼ)、麹(こうじ)、蒸米(むしまい)、仕込み水を組み合わせてタンク内で発酵させたもので、酒造りの中心的な工程となります。具体的には、酒母に水、麹、蒸米を数回に分けて投入し、糖化と発酵を進めることで、清酒の基盤を形成します。 醪の発酵が進むと、アルコールと二酸化炭素が生成され、液体部分が酒(原酒)となり、固形物が酒粕として分離されます。醪は一般的には酒類となる前の段階であり、酒税法においては発酵を行った原料の状態を...
詳細を見る関連用語
-
酒器
酒器とは、日本酒を運んだり飲むために使用する器や容器のことで、さまざまな形状や材質があります。代表的な酒器には、猪口...
-
清酒
清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄...
-
速醸系酒母
速醸系酒母とは、酒母(酛)の製造過程において、醸造用乳酸と純粋培養の酵母を初期段階で加えて作る酒母のことです。この手...
-
澱粉
澱粉(でんぷん)とは、植物が光合成によって生成する高分子化合物の一種で、主に多数のブドウ糖分子が結合して構成されてい...
-
相関係数
相関係数とは、二つの変数(例えば、日本酒のアルコール度数と甘さの感じ方など)の間にある直線的な関係の強さを表す数値で...
-
きょうかい酵母
きょうかい酵母は、日本醸造協会が選定し頒布する優れた清酒用の酵母です。この酵母は、酒造りにおいて重要な役割を果たして...