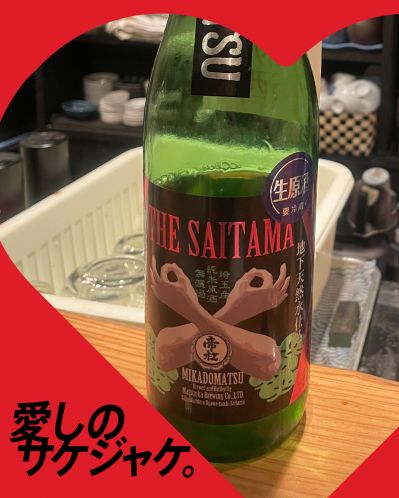灘目
下灘目郷(しもなだめごう)は、かつて存在した日本酒の産地であり、特に明和年間(1764年〜1772年)に「灘目三郷」として知られていました。この郷は、現在の灘五郷の西側に位置し、地域の酒造りにおいて重要な役割を果たしていました。しかし、時代の変遷とともにこの地域の酒造りは変化し、現在ではそれぞれの郷の名前は失われています。下灘目郷を含む灘目三郷は、歴史的な日本酒文化の一部として紀録され、当時の酒づくりの技術や風味に影響を与えた地域でした。
詳細を見る上灘目郷は、日本の兵庫県神戸市南東部に位置する地域で、現在の灘五郷の一部を成しています。この地域には西郷、御影郷、魚崎郷が含まれており、日本酒の生産が盛んなところです。明和年間(1764年〜1772年)には、上灘目郷と下灘目郷、および今津郷がまとめて「灘目三郷」と呼ばれることもありました。灘五郷は日本酒の名醸地として知られ、特に上灘目郷はその中でも重要な役割を果たしています。
詳細を見る今津郷は、兵庫県西宮市南東部に位置する日本酒の産地で、灘五郷の一つです。明和年間(1764年〜1772年)には、上灘と下灘が合併して「灘目三郷」と称され、歴史的な背景を持つ地域でもあります。今津郷は良質な水源に恵まれ、米の生産も盛んなため、酒造りに理想的な環境が整っています。地元の酒蔵では、伝統に基づいた技術を駆使して、風味豊かな日本酒が醸造されています。今津郷の日本酒は、その香りや味わいが特徴で、日本酒愛好者にとって魅力的な選択肢となっています。
詳細を見る辛口とは、日本酒の味わいの一つで、一般的に甘さが少なく、すっきりとした飲み口を持つことを指します。この表現は、ワインの「ドライ」に近い場合が多いです。辛口の日本酒は、通常、日本酒度がプラス(+)の数字で示され、数字が大きいほど辛口の印象が強くなります。 辛口の日本酒は、酸味やアルコール度数、香りの要素が絡み合い、個々の飲む人によって感じ方が異なることがあります。甘口と対照的に、辛口の酒は糖分が少なく、すっきりとした後味が特徴とされることが多く、和食やおつまみとの相性も良いとされています。
詳細を見る関連用語
-
山田錦
山田錦は、日本酒の製造において最も重要な酒造好適米の一つです。兵庫県の農業試験場で1936年に命名され、その後、日本を代...
-
清酒
清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄...
-
地酒
地酒(じざけ)とは、特定の地域で生産された日本酒を指します。通常、その地域の気候や水質、地元の米を使用して醸造される...
-
ヘテロ乳酸発酵
ヘテロ乳酸発酵とは、特定の微生物が糖類を乳酸に変える過程の一つで、ホモ乳酸発酵とは異なり、乳酸に加えて他の副産物も生...
-
涼冷え
「涼冷え」とは、日本酒を冷やして楽しむ際の温度帯の一つで、主に15℃前後の温度を指します。この温度帯は、日本酒の豊かな香...
-
汲水歩合
汲水歩合(くみみずぶあい)とは、仕込みに使用する水の量に対する米の重量の割合を示す指標です。この割合はパーセント(%)...