
- ニュース・トピック
フランスの和酒品評会「Kura Master 2025」で「超特撰 白鶴 天空 袋吊り 純米大吟醸 みとせ」が金賞受賞
白鶴酒造株式会社の「超特撰 白鶴 天空 袋吊り 純米大吟醸 みとせ 720ml」が、フランスの和酒品評会「Kura Master 2025」の純米大吟醸酒(36-50%)部門(※)で金賞を受賞しました。
当社はこの賞を受け、これまで以上に品質向上に努め、日本酒の美味しさを皆様にお届けします。
※()内の数字は精米歩合です。

「Kura Master」とは、2017年から開催されている、フランスの地で行うフランス人によるフランス人のための、和酒コンクールです。日本酒コンクールでは、サケ スパークリング部門、純米大吟醸酒(1-35%)部門、純米大吟醸酒(36-50%)部門、純米酒(51-65%)部門、純米酒(66-100%)部門、大吟醸酒部門、クラシック酛部門、古酒部門の8つのカテゴリーで、1,083点がソムリエやワイン専門家など135名によって審査されました。各カテゴリーから、プラチナ賞と金賞が決まりました。
(結果発表ページ:https://kuramaster.com/ja/concours/comite-2025/laureats/)
【純米大吟醸酒(36-50%)部門 金賞 受賞】
超特撰 白鶴 天空 袋吊り 純米大吟醸 みとせ 720ml
原材料名 :米(国産)、米こうじ(国産米)
精米歩合 :38%
アルコール分 :16%
▼商品特長
連綿と受け継ぐ技と志から醸した、香り豊かで繊細かつ深い味わいの白鶴が誇るシンボリック商品です。至高の酒米「兵庫県産山田錦」を高度に削り、“手洗い(洗米)”、“限定吸水(浸漬)”、昔ながらの手作業による蓋麹法、圧力をかけずに自然に滴り落ちる雫酒のみを集めた渾身の純米大吟醸です。氷温貯蔵で3年間熟成させることにより、まろやかさと香りが渾然一体となり、幅のある味わいに仕上がりました。林檎や洋梨様のフルーティーな香りが特長です。
数量限定(シリアルナンバー入り)。

▼商品ページ
https://www.hakutsuru.co.jp/product/sake/tenku/06476.html
▼販売店
全国の取扱酒販店
直営店(白鶴酒造資料館、白鶴御影MUSE、公式オンラインショップ)
「白鶴 天空」とは
原料米の選定、酒造り、パッケージデザインに至るすべてに、白鶴ができる “最高の技”を詰め込んだ、白鶴のシンボリック商品です。杜氏や蔵人といった造り手のみではなく、原料米の調達を行う者、高度なデータ分析により品質を支える者など、各工程を担うプロフェッショナルの技術が結集することで完成します。国内のみならず海外からも注目を集めるブランドで、現在「超特撰 白鶴 天空 袋吊り 純米大吟醸 みとせ」「超特撰 白鶴 天空 瓶内発酵 純米大吟醸 あわね」、「超特撰 白鶴 天空 中取り 純米大吟醸 山田錦」、「超特撰 白鶴 天空 中取り 純米大吟醸 白鶴錦」を展開しています。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】
白鶴酒造株式会社 お客様相談室
TEL:078-856-7190(休祝日を除く月~金 9:00~17:00)
白鶴ホームページ:https://www.hakutsuru.co.jp/customer/
▽ニュースリリース(PDF)
d13868-359-3efeba5aa87e73f4c705749ac5047e3d.pdf関連記事
-

- ニュース・トピック
フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―
2025/07/10
-
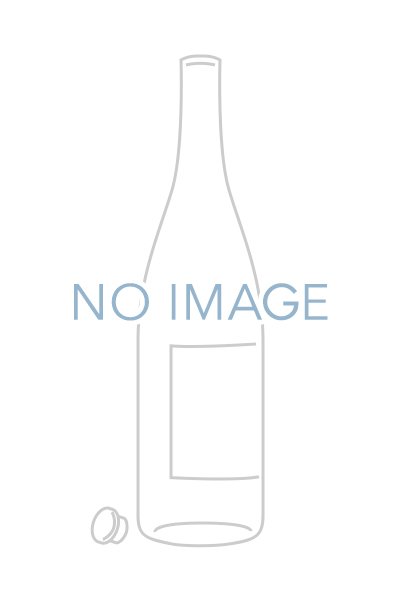
- ニュース・トピック
【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始
2025/07/08
純米大吟醸酒は、精米歩合が50%以下の白米と米麹、そして水を原料とし、吟味された方法で醸造される特定名称の清酒です。この酒は、吟醸造りという低温発酵の手法を用いて作られ、酵母が生み出す華やかな吟醸香とともに、すっきりとしたなめらかな味わいが特徴です。 純米大吟醸酒の製造過程では、原料米を50%以上削り、精米歩合を50%以下にする必要があります。また、原料の米麹は麹歩合15%以上を採用し、醸造アルコールや糖類は一切添加されません。このため、純度が高く、米本来の旨味や香りをじっくりと楽しむことができます...
詳細を見る限定吸水とは、浸漬工程において白米が必要以上に水分を吸収しないように、吸水時間を短縮する技術です。この手法は、特に吟醸酒の製造において重要で、米の中に適度な水分を保持させることで、香りや味わいを向上させることが目的です。過剰な吸水は、米の風味を損ない、酒質に悪影響を及ぼす可能性があるため、限定吸水によってコントロールされた水分量が、洗練された風味と香りを引き出す助けとなります。
詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...
詳細を見る大吟醸酒は、日本酒の中でも特に高品質な清酒に分類される特定名称酒です。製法品質表示基準に基づき、精米歩合が50%以下の良質な白米を原料とし、米麹と水、さらに必要に応じて醸造アルコールを使用して醸造されます。この製法では、低温でゆっくりと発酵させる「吟醸造り」が採用され、雑味を抑え、華やかな香りと滑らかな口当たりが特徴の清酒が生み出されます。 大吟醸酒の最大の魅力は其の優雅で気品溢れる味わいと、豊かな吟醸香です。固有の香味や色沢が特に優れたものが大吟醸酒とされ、醸造アルコールの使用は白米の重量の10...
詳細を見る袋吊りは、日本酒の上槽(じょうそう)における伝統的な方法の一つです。この工程では、醪(もろみ)を専用の酒袋に詰め、その袋を吊るして自然に滴り落ちる清酒を集めます。袋吊りでは、圧力をかけることなく、重力を利用してお酒を搾り出すため、非常に繊細な風味を持つ日本酒が得られます。この方法で得られるお酒は、斗瓶囲い(とびんがこい)や雫酒(しずくざけ)とも呼ばれることがあります。袋吊りは、特に高品質な日本酒の生産において重視されており、職人の技術と手間が反映された逸品となることが多いです。
詳細を見る蓋麹法(がいこうじほう)は、伝統的な製麴(せいこうじ)の技法の一つで、木製の盆である「麹蓋」を用いて麹を育成する方法です。この手法は在来の製麴技術として知られており、麹の糖化効率を高めるために特に吟醸酒の製造に適しています。一方で、麹の管理には手間がかかりますが、目指す麹の品質に導きやすい特徴があります。蓋麹法は、その精密な管理が求められるため、特に高品質な日本酒を醸造する際に多く用いられています。
詳細を見る純米酒は、白米、米麹、水を原料として醸造された清酒の一種です。精米歩合は70%以下で、米と米麹のみを使用しているため、添加物や醸造アルコールは一切含まれていません。このため、純米酒はお米本来の風味を存分に楽しむことができ、豊かな味わいを持つことが特徴です。 製法品質表示基準に基づいて、純米酒は特定名称酒の一つとして認定されています。この基準によれば、香味や色沢が良好であることが求められていますが、厳密な精米歩合の基準は設定されていません。一般的に純米酒は、しっかりとした味わいと芳醇な香りが楽し...
詳細を見る山田錦は、日本酒の製造において最も重要な酒造好適米の一つです。兵庫県の農業試験場で1936年に命名され、その後、日本を代表する酒米として認知されています。山田錦は、主に酒造りに適した特性を持っており、高精白が可能な心白を持っています。この特性により、吟醸酒や大吟醸酒の製造に特に重宝されています。 その栽培は非常に難易度が高く、倒伏しやすい性質や低い耐病性が課題とされますが、特に兵庫県三木市や加東市にある特A地区で生産された山田錦は、その品質が最上級とされています。心白が小さく、たんぱく質の含有が少...
詳細を見る原料米とは、日本酒を造るために使用されるお米のことを指します。一般的に「酒造好適米」または「酒米」と呼ばれる特別な品種のお米が選ばれ、これらは日本酒の風味や品質に大きく影響を与えます。酒造好適米は、粒の大きさや含まれる澱粉の量、そして精米しやすさなどが考慮されており、代表的な品種には山田錦や五百万石、愛山などがあります。これらのお米は、高い精米歩合(白米として使う際に削る割合)が求められることが多く、そのために精米技術が重要な役割を果たします。良質な原料米を使用することで、より豊かな風味や香...
詳細を見る中取り(なかどり)は、日本酒の醪(もろみ)を搾る際に得られるお酒の一部で、特にバランスの取れた香味が特徴です。搾りのプロセスでは、最初に出てくる液体を「あらばしり」と呼び、その後に続く中間部分が中取りです。最後に搾られる部分は「せめ」と呼ばれ、一般的にはそれほど風味豊かではありません。中取りは、醪の中でも最も旨味と香りが調和しており、酒米の特性や酵母がもたらす風味が存分に引き出されているため、飲む際には非常に高い評価を受けることが多いです。このため、中取りで造られた日本酒は、特に飲みごたえと...
詳細を見る雫酒(しずくざけ)とは、日本酒の製造過程において、特に吟醸酒や大吟醸酒を造る際に行われる方法の一つです。この製法では、醪(もろみ)を袋に入れて吊るし、自然の重力により酒が滴り落ちるのを待ちます。袋から滴り落ちる際に、最初に出てくる液体が雫酒と呼ばれます。この酒は、より濃厚で香り高い特徴を持つため、特に希少価値が高いとされています。雫酒は、手間暇がかかるため、限られた数量しか生産されず、その風味は非常に洗練されています。
詳細を見る「酒米」とは、日本酒の製造に使用される米を指します。この中には、「酒造好適米」と呼ばれる特に日本酒造りに適した品種と、日常的に食べられる「飯用一般米」も含まれます。日本酒の品質や風味に大きく影響を与えるため、酒米はその種類や特性が重要視されます。酒造好適米として広く知られているのは「山田錦」「五百万石」「愛山」などで、それぞれの特性が日本酒の味わいや香りに独自の個性をもたらします。一般米の中には、酒造用に使用できる品種もあり、それらも総じて「酒米」と称されることがありますが、通常は酒造好適米...
詳細を見る貯蔵とは、日本酒を火入れした後に一定期間寝かせて香味を熟成させるプロセスを指します。この期間中、日本酒は味や香りがまろやかになり、全体的なバランスが整います。一般的には、タンク内で熟成が行われますが、一部の蔵では瓶詰め後も低温で保管し、瓶貯蔵することがあります。このような貯蔵方法によって、酒質がさらに向上し、独特の風味が増すことが期待されます。
詳細を見る蔵人(くらびと)とは、日本酒を製造する酒蔵で、実際に醪(もろみ)づくりに従事する職人のことを指します。彼らは、杜氏(とうじ)と呼ばれる技術責任者の指導のもと、酒の仕込みや発酵管理などを行い、高品質の清酒を生み出す重要な役割を担っています。蔵人は伝統的な技術や知識を継承し、時には新しい製法を取り入れながら、米、水、酵母という基本的な原料から日本酒を造る熟練の技術者です。日本酒の風味や品質は、蔵人の技術と情熱によって大きく左右されます。
詳細を見る発酵とは、微生物が基質を分解し、エネルギーを得る過程のことを指します。日本酒の製造においては、主に酵母が糖をアルコールと二酸化炭素に変換することで、酒を醸造します。発酵は、呼吸と異なり、基質が完全に酸化されることはなく、その過程でアルコールや有機酸などの有用な物質が生成されるのが特徴です。これにより、酒独特の風味や香りが生まれ、風味豊かな日本酒ができあがります。発酵は、酒造りにおいて非常に重要な工程であり、温度や時間、酵母の種類などによってその結果が大きく変わります。
詳細を見る熟成とは、日本酒が一定期間貯蔵される過程を指します。この過程では、火入れを施した清酒をタンクや瓶に貯蔵し、時間をかけて風味や香りが変化していきます。新酒特有の香りが和らぎ、飲みやすいまろやかな味わいに変わることが特徴です。熟成により、酒の中に含まれる成分が相互に作用し、より深みのあるコクや複雑な旨味を生み出します。熟成は日本酒の魅力を引き出す重要な工程であり、適切な環境下で行われることで、酒質が向上します。
詳細を見る浸漬とは、日本酒の醸造工程における重要なステップで、洗浄された原料米を蒸す前に仕込み水に浸す作業を指します。このプロセスでは、白米の表面についている糠を水で洗い流し、米が必要とする水分を適切に吸収させます。吸水の時間は、使用する米の品種や年ごとの作柄、米の成分や硬さ、精米の度合いによって変わります。一般的には数分から数時間の間で、米が理想的な水分を含む状態を作り出します。その後、水切りをして次の日の蒸米に備えるのが目的です。浸漬は日本酒の風味や品質に直結するため、非常に重要な作業です。
詳細を見る洗米とは、日本酒の醸造工程において、精米後の原料米を洗浄する作業です。この工程では、白米の表面に付着している糠やその他の不純物を除去することが目的です。この際、洗米に使用する水は、米に水分を浸透させるための給水としても機能します。そのため、洗米の際には給水率を考慮して、浸漬時間を決定する必要があります。 洗米には、洗米機を使用する方法や、水輸送を利用した方法、さらには手作業で行う手洗いの方法があります。洗米によって、米の表面が清潔になるだけでなく、発酵の際に重要な酵素の働きを促進するための準...
詳細を見る杜氏(とうじ)とは、酒蔵において酒造り全般を指揮する最高責任者のことを指します。杜氏は、酒造りを担う職人集団の長であり、酒の品質や製法に大きな影響を与える存在です。地域によって南部杜氏や越後杜氏、丹波杜氏などと呼ばれる杜氏の集団があり、それぞれ異なる伝統や技術を持っています。そのため、杜氏が変わると酒の味やスタイルにも変化が見られることがあります。 近年、杜氏の平均年齢は約65歳に達し、後継者の育成が急務となっています。杜氏は、蔵の運営や醪(もろみ)の仕込み・管理といった重要な業務を行い、日本...
詳細を見る古酒とは、製造年度内に造られた新酒に対し、貯蔵期間を経て出荷・提供される日本酒を指します。一般的には、製造から3年以上熟成させた日本酒が古酒とされ、熟成によって味わいがまろやかになり、独特の深みを持つようになります。古酒の表示には明確な規定が存在しないため、3年や5年、さらには10年、15年といった長期熟成酒が有名です。長い熟成を経た日本酒は琥珀色の色調や複雑な香りを持ち、日本酒の中でも高価な部類に入ります。また、酒造業界では、酒造年度が変わると、それ以前に造られたすべての酒を古酒と呼ぶため、古酒の...
詳細を見る酛(もと)とは、日本酒の造りにおいて非常に重要な要素であり、醪(もろみ)を仕込む前に優れた酵母を大量に培養したものを指します。酛は酒母とも呼ばれ、この工程を酛造りまたは酒母造りといいます。酛の作り方にはさまざまな手法があり、主に速醸酛と生酛に大別されます。 速醸酛は、乳酸を添加することで酵母を育てる手法で、短期間で酒造りを行うことができるため、効率的な醸造が可能です。一方、生酛は、自然に存在する乳酸菌を利用する方法で、伝統的な技術が用いられます。また、山廃酛や菩提酛など、さらに多様な手法もあ...
詳細を見る
