
- ニュース・トピック
「仁喜多津 純米吟醸酒 さくらひめ酵母」が フランス開催の「Kura Master 2025」にてプラチナ賞を受賞

1895年(明治28年)創業の松山・道後地区唯一の造り酒屋である水口酒造株式会社(愛媛県松山市道後喜多町3-23)は、フランスで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2025」にて、「仁喜多津 純米吟醸酒 さくらひめ酵母」が純米酒(51-65%)部門でプラチナ賞を受賞いたしました。
Kura Masterとは
Kura MasterとはKura Masterは、2017年からフランスで毎年開催されている、フランス人を中心としたヨーロッパのプロフェッショナルが審査員を務める和酒コンクールです。審査員はフランス国家最高職人の資格を持つMOF保有者や、一流ホテルのトップソムリエ、バーマンなど飲食業界のスペシャリストで構成されており、特にフランスの歴史的食文化である「食と飲み物の相性(マリアージュ)」に重点を置いた評価を行っています。2025年度は第9回目の開催となりました。ブラインドテイスティングにより厳正な審査が行われ、その結果が発表されました。
仁喜多津 純米吟醸酒 さくらひめ酵母
<純米酒(51-65%)部門 プラチナ賞を受賞>
今回プラチナ賞を受賞した「仁喜多津 純米吟醸酒 さくらひめ酵母」は、愛媛テロワールにこだわり、新しい「えひめのお酒」として誕生した製品です。愛媛で生まれたデルフィニウム「さくらひめ」の花から抽出した「さくらひめ酵母」を使用しており、水口酒造ではトロピカルがテーマの「さくらひめ酵母 Type1」を用いています。さくらひめの花を想起させる華やかな香りと、果実のようなジューシーさも感じるバランスの良い酒質に仕上がっています。精米歩合は60%で、愛媛県産「しずく媛」を100%使用しています。クリームシチューやうなぎの蒲焼きなどのこってりとした料理や、ステーキなどの肉汁溢れる料理にも合う、食との相性の良さも兼ね備えた一本です。なお、本製品はInternational Wine Challenge (IWC) 2024の純米吟醸酒部門においてもゴールドメダルを受賞しており、国内外で高い評価を得ております。
今回のKura Masterでのプラチナ賞受賞は、「仁喜多津 純米吟醸酒 さくらひめ酵母」の品質が、食文化の専門家であるフランスのプロフェッショナルに高く評価された証であり、大変光栄に存じます。今後も、この受賞を励みに、国内外の皆様に喜んでいただける酒造りに一層邁進してまいります。

会社概要
水口酒造は、日本最古の温泉と言われる道後温泉の地で1895年に創業し、道後温泉本館と共に歩み続けている唯一の造り酒屋です。銘酒「仁喜多津」をはじめ、「道後蔵酒」、「道後ビール」など、多岐にわたる様々な酒類を製造販売しています。創業家には「暖簾を守るな、暖簾を破れ」という教えが伝わっており、伝統を継承しつつも常に新しいことに挑戦し、近年は「地産地消の酒造りプロジェクト」にも取り組むなど、地域と共に歩んでいます。全国新酒鑑評会での通算7度の金賞受賞など、数々の受賞歴を誇ります。私たちは、お酒が持つ「人と人、人とモノを繋ぐチカラ」を信じ、「道後から世界へ、世界から道後へ」を新たなビジョンとして掲げ、日本の「伝統的酒造り」の文化継承と発展に努めてまいります。
会社名:水口酒造株式会社
所在地:愛媛県松山市道後喜多町3番23号
創業:1895年(明治28年)
事業内容:酒類製造業(清酒・ビール・発泡酒・焼酎・リキュール・スピリッツ)
公式サイト:https://minakuchi-shuzo.jp/
お問い合わせ先
水口酒造株式会社(広報担当)
電話:089-924-6616
E-mail:info@minakuchi-shuzo.com
関連記事
-

- ニュース・トピック
フレッシュな味を保つ完全酸化防止サーバー「NOXY」先行販売開始― データ活用で日本酒文化の持続的発展に貢献 ―
2025/07/10
-

- ニュース・トピック
赤武酒造 × UNITED ARROWS 初のコラボレーションが実現~日本酒をもっと自由に、もっとスタイリッシュに~
2025/07/08
-
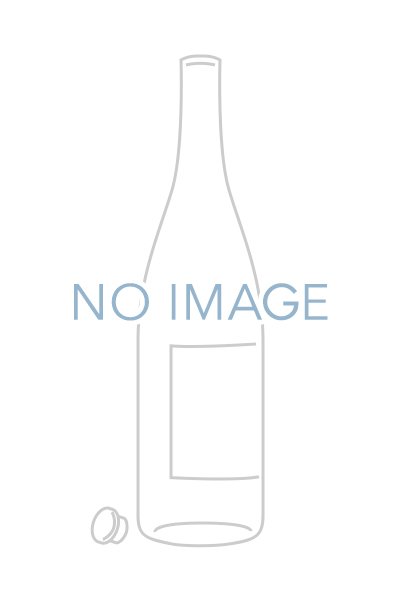
- ニュース・トピック
【イタリア初】ユネスコ世界遺産ドロミテに日本人酒蔵が誕生
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【ホテルシーズン日南】地元銘酒「飫肥杉」の酒蔵を訪ねる宿泊プランを7月1日より販売開始
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
【黒龍酒造 ESHIKOTO×meet tree】老舗が奏でる酒と美のハーモニー 『酒粕スキンケア』に待望の第2弾が登場
2025/07/08
-

- ニュース・トピック
ザ・リッツ・カールトン京都、日本料理「水暉」× 光栄菊酒造 復活の銘酒「光栄菊」を、日本料理「水暉」にて2か月間限定でご...
2025/07/08
全国新酒鑑評会は、独立行政法人酒類総合研究所が主催する日本酒のコンテストで、新酒の品質向上を目的として毎年開催されています。この鑑評会は、初回が1911年に行われて以来、100年以上もの歴史を誇り、日本酒業界で最も権威あるイベントの一つとされています。 審査の対象はその年度に醸造された新酒で、全国から出品された日本酒が厳しく審査されます。出品酒の中で特に優れたものは「入賞酒」として認定され、さらにその中から卓越した品質の酒が「金賞酒」として選ばれます。入賞酒や金賞酒には、製品にその受賞を示すラベルが...
詳細を見るマリアージュとは、特定の飲食物同士が互いに引き立て合い、新たな風味や体験を生み出す組み合わせのことを指します。日本酒と料理のペアリングにおいては、酒の味わいや香りが料理の食材や調理法と調和することで、双方の魅力を引き立て合います。例えば、濃厚な味わいの和食には旨みの強い日本酒を合わせることで、より深い味わいを感じられることがあります。このように、マリアージュを楽しむことで、食事の全体的な体験が豊かになり、さらに日本酒の多様性を発見することができます。
詳細を見る純米吟醸酒は、精米歩合が60%以下の白米と米麹、水のみを原料とし、吟醸造りと呼ばれる特別な製法で醸造された日本酒です。この酒は、華やかな吟醸香が特徴であり、フルーティーでクリスプな味わいを楽しむことができます。純米吟醸酒は、醸造アルコールや糖類が無添加であり、米本来の風味が最大限に引き出されています。 この酒は、低温でじっくりと発酵させることで、精密な味わいと香りのバランスを保っています。麹歩合は15%未満ではなく、使用されることが求められます。また、特定名称酒の一種であるため、合成添加物を用いず...
詳細を見る精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米した際に残る白米の割合をパーセントで示す指標です。具体的には、精米後の白米の重量を元の玄米の重量で割り、100を掛けることで計算されます。例えば、精米歩合が60%ということは、玄米の外側40%が削り取られ、残りの60%が白米として使用されることを意味します。 精米歩合が低いほど、より多くの外層が削られており、精白された部分が大きくなります。結果として、雑味が少なく、スッキリとした味わいの日本酒が造られることが多いです。一般的に、精米歩合が高い(外層を多く残してい...
詳細を見る純米酒は、白米、米麹、水を原料として醸造された清酒の一種です。精米歩合は70%以下で、米と米麹のみを使用しているため、添加物や醸造アルコールは一切含まれていません。このため、純米酒はお米本来の風味を存分に楽しむことができ、豊かな味わいを持つことが特徴です。 製法品質表示基準に基づいて、純米酒は特定名称酒の一つとして認定されています。この基準によれば、香味や色沢が良好であることが求められていますが、厳密な精米歩合の基準は設定されていません。一般的に純米酒は、しっかりとした味わいと芳醇な香りが楽し...
詳細を見る発泡酒とは、炭酸ガスを含んだお酒の一種であり、一般的にはビールとは異なる製法で作られる酒類を指します。発泡酒には、さまざまな原材料が使用されることがあり、米や麦、その他の穀物から作られたものがあります。日本においては、発泡酒はしばしば低アルコールの飲料として親しまれ、爽快感のある口当たりが特徴です。また、発泡酒は、香りや味わいが多様で、シャンパンやスパークリングワインのような華やかさを持つものから、より軽やかな飲み口のものまでさまざまです。通常、発泡酒は食事と共に楽しむことができ、特に和食と...
詳細を見る酵母とは、アルコール発酵に欠かせない単細胞の微生物であり、主に糖分を分解してアルコールと二酸化炭素に変える役割を果たします。日本酒の醸造においては、酵母の種類によって生まれる香りや味わいが大きく変わるため、目的に応じて様々な酵母が使い分けられます。例えば、吟醸酒では芳香成分を多く生成する特性を持つ酵母が使用されることが多いです。このように、酵母は日本酒の風味を左右する重要な要素であり、発酵力が強いことから、醸造やパン製造など多岐にわたって利用されています。酵母の選択が、最終的な製品の品質に大...
詳細を見る酒類とは、アルコールを含む飲料の総称であり、一般的には酒税法に基づいて定義されています。具体的には、アルコール分が1度以上の飲料が酒類に該当します。日本では、清酒、ビール、ワイン、焼酎など、多様な種類の酒類が存在し、それぞれの製法や原料によって特徴が異なります。また、酒類は文化や地域に根ざした飲み物であり、さまざまなシーンで楽しまれています。
詳細を見る焼酎とは、日本の伝統的な蒸留酒であり、主に二つのカテゴリーに分類されます。甲類焼酎は連続式蒸留機を使用し、アルコール分は36度未満で、一般的にホワイトリカーと呼ばれています。乙類焼酎は単式蒸留機を使用し、アルコール分は45度以下で、本格焼酎とされます。焼酎はウイスキーやブランデーなどの蒸留酒とは異なるため、法律上別のカテゴリに分類されています。 また、焼酎にはさまざまな種類があり、乙類焼酎の場合、主原料によって多様な製品が存在します。例えば、米を主原料とする米焼酎、さつまいもを使ったいも焼酎、麦...
詳細を見る清酒(せいしゅ)は、日本酒を指し、米と水を主成分として発酵させて作られる酒類です。醪(もろみ)を漉すことによって、澄んだ酒に仕上げられる点から「清酒」という名称が生まれました。また、清酒は特に醸造アルコールを添加せず、純粋に米の成分から生成されたものを指す場合が多いです。飲み方や提供方法も多様で、和食との相性が良く、冷やしても、温めても楽しむことができます。最も代表的な日本の伝統的な酒であり、国内外で高く評価されています。
詳細を見る
