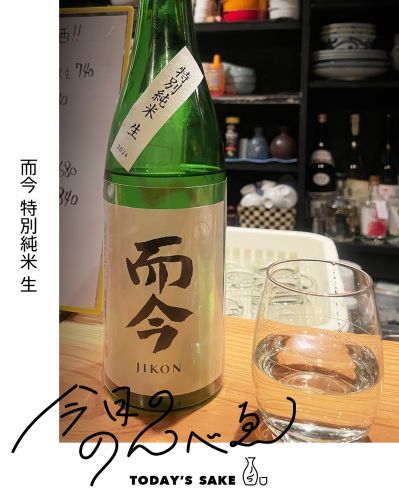承認基準
アルコール添加とは、上槽前の醪(もろみ)にアルコールを加える製造方法のことを指します。第二次大戦後の原料米不足を背景に、昭和18酒造年度からこの手法が認められるようになりました。当初は米の不足を補うための手段として導入されましたが、現在では清酒の香味を軽快にする目的や、製造コストの削減を図るために行われています。アルコール添加によって、酒の風味や飲み口のバランスを調整し、様々なスタイルの清酒が生み出されています。
詳細を見る増醸割合とは、日本酒の製造において、増醸酒用の原料として使用される白米の数量が、その酒造年度における全ての白米数量に対して占める割合のことです。この割合はパーセント(%)で表され、承認基準においては23%以内であることが定められています。増醸酒は、通常の酒よりも手頃な価格で提供されることが多く、そのために製造過程での白米の使用割合を調整することが行われます。これにより、味わいや品質を保ちながら、コストを抑えた日本酒が生まれるのです。
詳細を見る醸造酒とは、原材料を発酵させることによって作られる酒類の総称です。主に米や麦、ぶどうなどの穀物や果実を使用し、酵母の働きによってアルコールが生成されます。日本酒(清酒)、ビール、ワインなどがこのカテゴリーに含まれます。これらの酒は、発酵による高い香りや味わいを持ち、文化や食事と深く結びついた楽しみ方がされます。醸造酒は、原材料や製造方法によって多様なスタイルが生まれ、各地域の特性を反映したものとなっています。
詳細を見る増醸酒(ぞうじょうしゅ)は、主に三倍増醸法を用いて醸造された清酒です。この方法では、酒の製造過程で雑酵母を用いて元の酒の量を三倍まで増加させることで、より多くの日本酒を生産します。増醸酒は多くの場合、価格が手頃で香りや味わいが軽やかなので、日常的に楽しむことができる日本酒として人気があります。ただし、純米酒や本醸造酒に比べると、風味や香りの深みはやや劣るとされています。
詳細を見る白米とは、玄米から精米され、胚芽や米の表面が削除された米のことを指します。精米の過程で外皮や殻が取り除かれ、主に澱粉部分が残るため、白くて光沢のある状態となります。白米は日本酒の醸造において非常に重要で、精米歩合によって酒の風味や香りに影響を与えるため、特に品質の高い日本酒には厳選された白米が使用されます。一般的には、精米の度合い(粉砕の割合)が低いほど、良質で洗練された酒を生み出す傾向があります。
詳細を見る関連用語
-
酒税法
酒税法とは、日本における酒類に課税するための法律であり、酒類の製造、販売、流通に関する基本的なルールを定めています。...
-
吟醸香
吟醸香とは、吟醸造りの日本酒に特有の香りで、主に花や果物を思わせる華やかな香りを指します。この香りは、酵母由来のエス...
-
貴醸酒
貴醸酒は、伝統的な日本酒の製造方法の一つで、仕込みの際に水の代わりに清酒を用いることで造られます。この手法は主に三段...
-
短時間浸漬
短時間浸漬とは、日本酒製造において米が水を吸収する時間を短くする技術です。この方法は、特に吟醸酒の製造において重要で...
-
貯蔵年数
貯蔵年数とは、日本酒が貯蔵容器に保管されてから出荷されるまでの期間を指します。この期間は、製法品質表示基準に基づいて...
-
火落ち
火落ち(ひおち)とは、日本酒の製造過程において、火落菌(ひおちきん)が増殖することで発生する現象を指します。これによ...